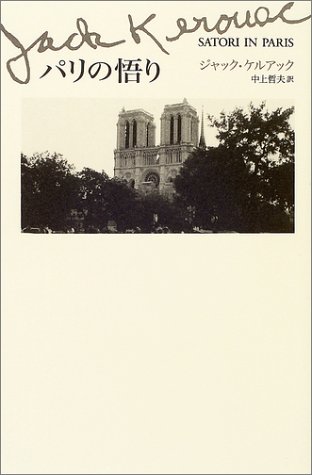マイケル・ジャクソン(2):母と曾祖父の美声を受け継ぐ
きつく低賃金の仕事をしていた父は、「音楽」;ショービジネスに乗り出した
弟たちとバンド「ザ・ファルコンズ」を結成。家での練習を見ていた子供たちジョーが北部のイースト・シカゴにまで来たのは、仕事ではなく父サミュエルの女癖のせいでした。長男ジョーだけを連れてオークランドに移り住んでいたサミュエルは、3度目の結婚をし、厄介者になったのを感じたジョーはイースト・シカゴに移り暮らしていた母と弟妹たちの許へひとり向ったのでした(その時期、母の実家がイースト・シカゴにあった)。
そしてハイスクール2年の時、学校を中退、ゴールデン・グローブスのボクサーになったのです。高校を中退してボクサーになったということは、自身の内から湧き上がるエネルギーの放出と現状を打破していこうとする強い意志のあらわれです。
製鉄場で埋没していたジョーが、好きだった「音楽」に乗り出そうとした企ても、ボクサーになった時のように、潜行する”何か”への訴えの答えでした。
60年代に入ると製鉄の町は衰退しはじめています。ジョーは何度も首切り(レイオフ)にあい、溶接工の仕事に就いたり、ジャガイモの収穫の仕事をしたり、再び製鉄の仕事をみつけたりしていたといいます。ジャガイモの収穫の仕事をしていた時は、家族の食卓はいつもジャガイモ料理ばかりになったといいます。
そんな苦難に甘んじていた元ボクサーのジョーが、「音楽」という別のリングに上がろうとしたのです。かつてリングの上でスポットライトを浴びたように、新たなリングの「ステージ」でスポットライトを浴びたかったのです。
ジョーは弟ルーサーを呼び込み、リズム&ブルースのバンド「ザ・ファルコンズ」を結成しました。地元やシカゴのクラブやバーやカレッジでも演奏したため、「ザ・ファルコンズ」はジャクソン一家にも僅かながら臨時収入になりました。
リハーサルがジャクソン家のリビングでおこなわれたので、年長の兄弟ジャッキー、ティト、ジャーメインは夢中になって父たちの演奏に見入っていたといいます(とくにティトは学校でサックスを習っていて音楽的感性も高く、後に父ジョーは音楽的才能を継ぐ者としてティトに目をかけていた。またマイケルは年齢的に「ザ・ファルコンズ」のことは覚えていない)。
が、「ザ・ファルコンズ」は、ショービジネスの世界でジョーが目論んだようにはうまくいかず、結局、解散してしまいます。ジョーはギターをベッドルームの押し入れに隠すように押し込み、以降子供たちの前でギターを演奏しようとはしませんでした。
子供たちにギターに指一本触れさせることなく、また子供たちも父を怖れ、ギターに触れようとはしませんでした。ある日、ジャッキーとティト、ジャーメインが母がキッチン仕事をしている間に、こっそりとギターを取り出し、ラジオのボリュームを上げてギターの音がわからないように演奏しだしたのです。
その頃、マイケルも母に喋らないことを条件に彼等の演奏を見ることを許されます。が、母は気づいてしまいます。最初は怒った母でしたが、治安の良くない戸外でワルな少年たちに誘い込まれるより、子供たちが仲良く部屋で過ごす方がよいだろうと判断し、ジョーに内緒にするからギターを大切に扱うようにはからってくれたのです(自伝『ムーンウォーク』より)。
この辺りの事情は、父ジョーが子供たちが同年代の子たちと家の外で会ったり、遊んだりするのを絶対許してもらえなかった、同世代の子たちと一緒に遊べたのは学校だけだったと語るジャッキー(上から2番目)の言葉を載せている『マイケル・ジャクソンの真実』とは少し異なっています。
しかし同著には、鉄鋼の町ゲーリーが衰退しだし、治安がさらに悪化し物騒になり、ストリートにはワルな連中が増え、ジョーもキャサリンも子供たちがいつ何時巻き込まれないかいつも心配していたという記述もあるので、親の心配性と子供たちの外で遊びたいという気持ちが裏腹だったことがわかります。
どうやら子供たちを戸外になるべく出させないようにしていたのは、『聖書』の教条的な文句や厳しい躾から同世代の子供たちと接触させたくなかったため、というのではないようです(まま伝記にはこうした記述があるが、実際にワルな連中に感染させたくなかった思いと、ジョーが父から受け継いだ子供たちに対する気質的な厳格さが相乗して結果そうなったようです)。
母キャサリンはジョーが仕事中に、こっそりそのギターを取り出し、リビングルームに子供たちを集め、喜ぶ子供たちのために弾き、一緒に歌いだしたのです。リズム&ブルースではなく、キャサリンが好きなカントリー&ウェスタンの曲でした。もともとジャクソン家には「音楽」がいつも満ち溢れていたので、子供たちは大喜びでした。
マイケルの声は、母、そして母方の曾祖父の美声を継いだものだった
ギターなど「楽器」を弾けたように、父ジョーだけでなく母もまた大の音楽好きで、ギター以上にクラリネットやピアノを巧みに弾きました。しかもジョーよりもうんと前にバンドに属していたのです。
キャサリンは姉妹で教会のジュニア・バンド、さらには高校のオーケストラに所属し、聖歌隊のメンバーでした。「音楽」とのつながりは、おそらく父ジョーよりも長く、しかもキャサリンの家系数世代にわたっていたのです。マイケルは後に語っています。「自分の声は、母から受け継いでいる」と。そして自身も美声をもっていた母もまた思っていました。「やはり血なんだ」と。
それは以前に、曾祖父ブラウン・スクリュースが素晴らしい「美声」の持ち主だったことを聞いた時もまた感じたことだったのです。曾祖父ブラウンの声は、他の誰よりも朗々と響き、教会の建物を通り抜け、教会のある渓谷中に木霊(こだま)したといいます。
曾祖父ブラウンは、南部アラバマ州の綿花の小作農でした(姓のスクリュースは、奴隷として仕えていたスクリュース家の名をつけたもの)。ブラウンは毎週日曜日にラッセル郡の教会に集い、賛美歌を歌っていたのです。
その美声は一帯に知れ渡っていたそうです。祖父もまた綿花の小作農として働き、キャサリンの父となるプリンス・スクリュース(マイケスの母方の祖父)もまた綿花の小作農でしたが、セミノウル鉄道でも働くようになっていました。3世代にわたってずっとアラバマ州に暮らしていました。
1930年にキャサリンが誕生します。が、生後18カ月の時、キャサリンはポリオ(小児麻痺)に罹っています。まだワクチンがなく、罹患した者は亡くなるか、脚が不自由になるかという時代だったといいます(キャサリンは脚が不自由に。その障害は生涯続く)。
そして父プリンスがなんとか定職を求めようとして移り住んだのが、マイケルらジャクソン兄弟が誕生したインディアナ州ゲーリーだったのです。キャサリンの父プリンスは、ジョー・ジャクソンと同様、USスチールの製鉄工場の仕事に就くのです(その後、まだ若かったプリンスはイリノイ・セントラル鉄道で特別客車のボーイの仕事をみつけている)。
ゲーリーに住み着いてわずか1年たらずで、キャサリンの両親は離婚します(キャサリンの母マーサは子供とゲーリーにとどまりまる)。キャサリンは16歳になるまで脚が不自由だったため松葉杖をつき、歯に矯正用ブレスもつけていたこともあり、よくからかわれたため引っ込み思案になってしまったといいます。
入退院を繰り返えしながら学校に通いましたが結局、高校は卒業できませんでした(大人になってから高校資格取得クラスを受講し卒業証書を得ている。また脚の不自由さは大人になってからも残ることに)。
学校に良い思い出のない母。「音楽」だけが楽しみだった母
学校ではほとんど良い思い出もないキャサリンにとって、当時「音楽」だけが楽しみだったようです。妹ハティと、ラジオのカントリー&ウェスタン番組を聞くのが唯一の楽しみだったといいます(ちなみにカントリー音楽は、キャサリンの家族が代々暮らしていた米国南部で発祥した音楽で、ヨーロッパの民謡やケルトの音楽に南部の教会の霊歌のゴスペルや賛美歌が混じり合って生み出されたものです。
カントリー&ウェスタンと「ウェスタン」がつくことがあるのは、後にハリウッド映画やブロードウェイ・ミュージカルの影響で、カントリー・ミュージシャンが当時人気を博していた西部劇風の小道具や演出;カウボーイハットやブーツを取り入れたためでした)。
キャサリン姉妹が好きだったカントリー&ウェスタン音楽が、白人ミュージシャンの奏でる音楽だったことは、母親っ子だったマイケルが、”白人”へのオブセッションを持ち続けただけでなく、その音楽も、黒人と白人のサウンドを”融合”したものだったことを考えれば、すでにその源流の一筋が母の「心の樹」に宿っていたことに気づかされます。
キャサリンはハンク・ウィリアムズやアーネスト・タップスのカントリーミュージックの熱狂的ファンで、幼子マイケルを腕の中に抱いてよく歌ったのもまた白人ミュージシャンのジミー・デイビスとチェールズ・ミッチェルが歌った「ユー・アー・マイ・サンシャイン」(1940年公開の映画「Take Me Back to Oklahoma」の挿入歌)や「コットン・フィールズ」だったのです。
学校にも充分に通えず引っ込み思案だったキャサリンが、そんな大好きなカントリー・ミュージックに酔いしれるようになったとき、うっすらとあった女優への夢や憧れは、歌手になる夢へと変じていったのです(キャサリンはシアーズでパートタイムをしていた)。そしてその夢は別のかたちをなして芽吹いていくのです。自身と曾祖父の声が継がれて。
・参照書籍『ムーンウォーク;マイケル・ジャクソン自伝』河出書房新社/『マイケル・ジャクソン・レジェンド』(チャス・ニューキー=バーデン著 AC Books/『マイケル・ジャクソンの思い出』坂崎ニーナ・眞由美著 ポプラ社/『マイケル・ジャクソン;孤独なピーター・パン』(マーク・ビゴ著 新書館)/『マイケル・ジャクソンの真実』J.ランディ・タラボレッリ著 音楽之友社)/『マイケル・ジャクソン The King of POP 1958-2009」青志社
マイケル・ジャクソン(1):父と祖父は厳格な気質だった
マイケルの声は、母、そして母方の曾祖父の美声を継いだもの。USスチールの製鉄所に職を求め北上した両親の家族。祖父の厳格な気質を継いだ父ジョー
はじめに:
「This is it これだ!」と叫ぶまで、無我夢中になって「完璧」さをめざすわずか5歳からステージに立ち、兄弟で結成されたジャクソン5のリードボーカルとして子供時代から脚光を浴び、「キング・オブ・ポップ」として頂点にのぼりつめたマイケル・ジャクソン。
とくに『スリラー』『Beat It』『ビリー・ジーン』などのミュージック映像は、音楽シーンを新しい次元を生み出し、史上最高のレコードセールスを叩き出しました。
あまりにも早熟だったマイケルでしたが、奇怪で不可解な行動や噂が飛び交いだした大人になっては、真逆に心の中の「ピーター・パン」を、巨大な「ネバーランド」に遊ばせ、それがまた「変人マイケル;Wacko Michael」のイメージを増幅させました。
幾冊もの伝記やドキュメンタリー映像にくわえ、自伝『ムーンウォーク』(1988年刊 30歳の時)も出版されるなか、今では多くの秘密も露呈されることになっています(情報が飛び交い余計見えにくくなったものも多い)。
自伝『ムーンウォーク』から伝わってくるのは、「This is it!これだ!」と叫び、徹底的に納得するまで、無我夢中になって「パフォーマンス」と「クリエーション」を永遠に繰り返すマイケルの姿です。その「完璧」さは、ミケランジェロのシスティナ礼拝堂の天井壁画のように「完璧」なものでなければならないんだと、マイケルは生前語っています。
後のすべてにわたるヴィジュアル・センスの源流の一つは、幼い頃から「絵」を見ることが大好きだったことにあるようです。そして歌やダンス、パフォーマンスへの絶えざる追求の上に、「映画」(とくにホラーやSF、ファンタジーなどの映画 B級映画も含む)「写真」への関心と好奇心がそこに加わり、『スリラー』などのミュージックビデオ(マイケルはそれをショート・フィルムと呼んでいた)に合流していったのです。
またディズニーランドのアトラクション「キャプテンEO」の製作に参加した時には、ウォルト・ディズニーの伝記本を何冊も読んでいたり、玩具やゲーム、コミック類への熱中だけでなく、興味が惹かれるものに関する読書もつねにかかさなかったようです(日本公演終え帰国後、古代日本が中国と陸続きになっていたことを、おそらく本を通して知って驚き、知人に電話で確認している)。
さてマイケル・ジャクソンの「マインド・ツリー(心の樹)」は、ジャクソン・ファミリー抜きに存在することはありません。ジャクソン・ファミリーは、まるで一つの”惑星”のようでした。その”惑星”が、間違いなくマイケルの”土壌”になっていますが、その独特の”美声”は、母方の祖父から星を継いできたといわれています。
「ムーンウォーク」の原型はすでにこの世に存在していましたが、研ぎすまされた感性でそれを吸収したマイケルが、”アレンジ”しながらつくりだしていったものでした。
それではまず、ジャクソン・ファミリーという一つの”惑星”に着陸してみましょう。そこはシカゴの東部、ミシガン湖に面した鉄鋼都市、アフリカ系アメリカ人の割合が全米で最も多く、犯罪発生率が全米でも最も高い場所の一つに数えられた白煙で煤けた土地です。
大人になったマイケルの歩幅で、玄関を入って5歩も歩けば通り抜けてしまう(マイケルの言葉)小さな「家」、それがマイケルの”惑星”でした(まさにムーン・ウォークすればたちどころに外の空へと抜けでてしまうほどの小さな家だった)。
南部から北上した両親のファミリー、
栄枯盛衰の人工鉄鋼都市に生まれる
マイケル・ジャクソン(Michael Joseph Jackson)は、1958年8月29日、ミシガン湖に面したインディアナ州の製鉄の町ゲーリー(Gary ゲイリーとも)に生まれています。シカゴのダウンタウンから南東に40キロ程で、シカゴ・メトロポリタン・エリアに属し、「Magic City of Steel 」とか「City in Motion」をニックネームにするゲーリー(人口10万人程)は、つぎの5点で全米にもよく知られる町となっているようです。
まず最初に圧倒的な「黒人の町」(人口の84パーセント余)であること、そして全米で最も早く黒人市長が誕生した町であること(1967年)、USスチールの巨大製鉄工場や煙突が林立していること、その凋落、そしてジャクソン5やマイケル・ジャクソンが誕生した町であること(全米ツアーを故郷ゲーリーからスタートしたことがある)。
そして"デンジャラス”極まりない町、ずっと高い犯罪率です。2000年に入ってから犯罪率が2年連続で全米トップだったこともある程です(年間の殺人は70人余で全米の他の地方都市の8倍を超える)。
じつは製鉄の町ゲーリーの急激な隆盛と衰退が、「ジャクソン・ファミリー」を生み出す重要な背景となっているのです。なぜゲーリーが全米にも聞こえる「黒人の町」になったか。それは巨大鉄鋼カンパニーのUSスチールがこの地に製鉄所を建設し、安い賃金で使える大量の労働者を必要としたからです。なんとUSスチールが製鉄所を設立する前は、ゲーリーという町は存在しなかったのです(ゲーリーという町名は当時のUSスチールの社長の名前です!)。
マイケル・ジャクソンの父方の先祖も、母方の先祖も、それぞれ南部のアーカンソー州とアラバマ州に暮らしていました。そして奴隷解放後、各々の一家は職を求め南部から北部へと流れ、米国製鉄業が沸騰しはじめたイースト・シカゴに向ったのでした(実際の町名イースト・シカゴは、ゲーリーの西隣の町のこと)。
マイケルの父ジョゼフ・ウォルター・ジャクソン(通称ジョー)は、実際USスチールの関連会社インランド製鉄でクレーンの操縦士をし、マイケルの母キャサリンの父も同地で製鉄工場の仕事に就いています(後にイリノイ・セントラル鉄道で特別客車のボーイの仕事に就く)。
父ジョーは、子供たちを戸外で遊ばせないような祖父の厳格な気質を継いでいた
まずはマイケルの父方のジャルソン家を少し辿ってみます。
よく知られるマイケルの父ジョーの鉄拳制裁をいとわないその厳格な気質は、じつはジョーが父サミュエル・ジャクソン(マイケルの祖父)から受け継いでしまったものだった気質そのものだっただけでなく、父ジョーがマイケルだけでなく兄弟姉妹全員を同年代の子たちと家の外で会ったり、遊んだりするのを許さなかったりしたのは、祖父サミュエルが息子のジョーら子供たち(ジョーは5人兄弟の長男)にしていたことだったのです。
子供たちを口喧しく躾けた祖父サミュエル・ジャクソンも父ジョーも、自身の恋愛面にはゆるく、高校教師だった祖父サミュエルの妻は教え子クリスタルでしたし、ジョーも再婚で、キャサリンと結婚してからも浮気心が静まることはなかったようです(別の女性と一児をもうけている)。また繊細だったけれどもよそよそしく近寄りがたい性格だったこと、家族に滅多に愛情を見せなかったこと、など祖父と父は瓜二つなのです。
祖父サミュエルや父ジョーが、なぜ子供たちが家の外で友達と会うのを好まなかった(あるいは許さなかった)のか。それは「悪い奴とつき合うと、若者の性質が台無しになる」という『聖書』の言葉によっていたともいわれています。もともと南部は「バイブル・ベルト」と呼ばれる程、『聖書」はよく読まれていました。
しかし、女性関係だけは、祖父サミュエルや父ジョーだけでなく、キャサリンが以前属していたバプティスト派とルーター派の牧師も同じだったのです(キャサリンは牧師たちが外で女性たちと付き合っているところを目撃している。自身の家族の失敗から異性関係に潔癖性だったキャサリンは、さらに厳格な「エホバの証人」に向うことに。
「エホバの証人」は白人中心だったが、精神的な行き場が失われた低所得者層の黒人にも強くアピールすることとなり、かなり多くの黒人たちが入信している)。
マイケル・ジャクソン(2)へ続く:
・参照書籍『ムーンウォーク;マイケル・ジャクソン自伝』河出書房新社/『マイケル・ジャクソン・レジェンド』(チャス・ニューキー=バーデン著 AC Books/『マイケル・ジャクソンの思い出』坂崎ニーナ・眞由美著 ポプラ社/『マイケル・ジャクソン;孤独なピーター・パン』(マーク・ビゴ著 新書館)/『マイケル・ジャクソンの真実』J.ランディ・タラボレッリ著 音楽之友社)/『マイケル・ジャクソン The King of POP 1958-2009」青志社
アーサー・C・クラーク(3):本屋でH.G.ウェルズの『宇宙戦争』を立ち読み
お小遣いで買えず、昼休みに本屋で1週間かけてH.G.ウェルズの『宇宙戦争』を立ち読み。オラフ・ステーブルドンの『最後の、そして最初の人間』に<宇宙観>をくつがえされる
スリランカ・コロンボで暮らしていたアーサー・C・クラークのオフィス兼自宅の様子や、晩年までスキューバダイビングをしていたことなど、取材とアーサー・C・クラーク自身からのメッセージ
アーサー・C・クラーク(2)から:
グラマースクールの地下の溜まり場で見つけた『アスタウンディング』誌
アーサー・C・クラーク(2)から:
中等教育(中学校)は、家から8キロも離れた内陸に入りこんだ街トーントン(Taunton)にあるヒューイッシュ・グラマースクールに入学しています(クラーク少年は、19歳に公務員になるまで8年間ずっとこのグラマースクールに通っています)。
このスクールには広い地下室があり上級生のための勉強部屋とされていましたが、またの名を”地下牢”とも呼ばれていたスペースでした。そこには上級生たちが持ち込んだいろんなものが散乱していました。
その中に、クラーク少年は自身の将来の軌道をさらに決定的にするものを偶然見つけたのです。それはある不思議な絵が描かれた雑誌でした。
その表紙にはあちこちに孔が穿(うが)たれた天体に向って空飛ぶ潜水艦のようなものが突き進んでいる絵が描かれ、「Brigands of the Moon 月面の盗賊 ー陰謀と冒険の血沸き肉踊る惑星間小説」(作者:レイ・カミングス;27歳から5年間トーマス・エジソンの個人秘書となり、後にSFパルプ小説の生みの親の一人に。日本には同タイトルで1931年に翻訳)と印刷されていたのです。
描かれた天体がクラーク少年が大好きだった「月」だったことも重なり、クラーク少年は、とびきりの「センス・オブ・ワンダー」を覚え、くらくらしたといいます。
その雑誌は、キリー家で目にした『アメージング・ストーリーズ』誌ではなく同じくアメリカで出版されていた『アスタウンディング』誌(1930年3月号)でした。クラーク少年は持ち主がいないことをしると家に持ち帰り隅から隅まで読んだのです。その頃、嫌気がさしていた幾何学や代数、ラテン語の勉強をほっぽりだして『アスタウンディング』誌のバックナンバーを集めはじめました。
ウールワース・ストアで1冊たった3ペンスで売っていることを知り、しこたま「パルプ雑誌」を手に入れることがきました。当時「パルプ雑誌」は貨物船のバラスト(重量のバランスを取るために積め込む重し)として用いられていたので、米国帰りの貨物船から大量に放出されていたのです。
クラーク少年はコレクションの索引もつくり、数年の間に『アメージング・ストーリーズ』誌や『ワンダー』誌の蒐集もかなりのものになっていきました。
その間に、クラーク少年はイギリスの少年雑誌も目を通しはじめています。『ボーイズ・オウン・ペーパー』『メカーノ・マガジン』『マグネット』誌でした。アメリカの「パルプ雑誌」からの転載記事や作品もあったので、クラーク少年にとっては要注意だったのです。
お小遣いで買えず、昼休みに本屋で1週間かけてH.G.ウェルズの『宇宙戦争』を立ち読み
グラマースクール時代には、「パルプ雑誌」だけでなく単行の小説も数多く読んでいますが、小説といわれるもののほとんどは「SF」ものでした。学校の昼食時、素早く昼食をすませ必ず向う場所はW.H.スミス書店のトーントン店でした。「立ち読み」に行ったのです。
そこでH.G.ウェルズの『宇宙戦争』に出会っています。本の値段は数シリング。けれどもわずかなお小遣いでは手がでません。クラーク少年は、日参し1週間程で『宇宙戦争』を読破します。その日読んだ最後の頁の隅を店主に見つからないようにこっそり折り、翌日またそこから読みだすのです。
そうやって何冊ものペーパーベックのSF本を読破していったといいます。テレビ時代の到来はまだ先で、書店の店主ものんびりしたものだったといいます。
H.G.ウェルズを”発見”したのとほぼ同じ頃、ジュール・ヴェルヌを”発見”しています。後になんとかして手に入れた『月世界旅行』と『海底2万里』は、クラーク少年のお気に入りになりしました(『地底旅行』は晩年までずっと手放さず持っていました)。
オラフ・ステーブルドンの『最後の、そして最初の人間』に<宇宙観>をくつがえされる
ハードカバー本に関しては、トーントンにある町の公共図書館にあることがわかってからというもの手当たり次第に借りまくっています。
最低でも1日に1冊は借りていたといいます。学校帰りに図書館に寄って幾らか読んで、8キロもある家まで自転車で帰り、夜には家の仕事を手伝い、それからの寝るまでの時間を読書にあてていました。
その頃読んだものの中では、ライダー・ハガードの『世界が震えたとき When the World Shocked』とコナン・ドイルの『失われた世界』がクラーク少年にとって最高傑作でした。
そしてクラーク少年の「想像力」に最高レベルの衝撃を与えたのは、オラフ・ステーブルドンの『最後の、そして最初の人間 The Last and First Man』(1930年)だったといいます。
クラークはこの本が出版された直後に、住んでいた町の図書館(マインヘッド公共図書館)の棚で見つけたのでしたが、人生の晩年になってもその時の情景をしっかり思い出すことができるといいます。『最後の、そして最初の人間』は、クラーク少年の<宇宙観>を根底から変えてしまったほどの影響力があり、後のクラークの作品の多くに影響を与えていったのです。ある意味、英国サマーセット州の地面に張っていた”根”が根こそぎ引っぱりだされ、宇宙空間に向けて上空に放たれたような感じだったにちがいありません。
14歳、父が亡くなる。母は農場の経営をしながら子供たちを懸命に育てた
14歳の時(1931年)、父が亡くなります。父からすれば、電気通信技師としての復員士官だった父にとって慣れない農作業から解放されたのでした。解放されないのは母で、4人の子供を抱え生活は厳しくなります。
クラーク少年にしてみれば、母が農場の経営だけでなく、乗馬のレッスンやケアンテリア犬の飼育、植物の有機的な栽培、さらには宿泊客を受け入れるなど、仕事を増やし忙しそうにしているようにみえたのですが、それも欠損続きの農場経営の埋め合わせをするためのものだったのでした。
クラークは大人になってから、父が亡くなってからというもの母はいつもお金に困っていたことを知ったのです。クラーク少年は家の事情はつゆ知らず、手製の望遠鏡でいつも「月」を見ていました。
故郷マインヘッドからは360度、素晴らしい円天の空が眺められ、クラーク少年の「心の樹」は、ジャックの豆の木のように大空に向かってするすると伸び上がっていくのでした。天体観測はクラーク少年の心の成長に欠かせないものとなっていました。
そして「月」や「宇宙」への関心が高まれば高まるほど、「パルプ雑誌」もうず高く積み上がっていくのでした。クラーク少年の「月」に関する知識は、故郷マインヘッドのことよりも詳しくなっていたのです。
17歳の時、できたばかりの「英国惑星間協会」に入会。先端の科学技術情報の重要性を知る
月や宇宙への関心は、なにもクラーク少年にだけ特有にあらわれたものではありませんでした。1930年代、英国中で若者や子供たちの眼が宇宙空間に注がれはじめていたのです。1933年、クラーク少年16歳の時、ロンドンで非営利団体の「英国惑星間協会 British Interplanetary Society(BIS)創立者P. E. Cleator」が発足しています。
英国惑星間協会は、月に向って人類を打ち上げる月ロケット構想を打ちだしていたためクラーク少年が黙って見過ごすことはありませんでした。クラーク少年は翌年、英国惑星間協会に入会、「月」と「宇宙」へ科学的側面からの関心を高めていきました。
英国惑星間協会は、英国の爆発物法によって禁止されている液体燃料を用いたロケットの発射テストではなく、個体燃料を用いた多段式ロケットで充分な速度を調達できること、月着陸船(Lunar Module)や重力のことなど突っ込んだ科学的議論を交わしていたのです。
クラーク少年は、入会した年から毎月発行される「月刊英国惑星間協会 Journal of the British Interplanetary Society」を購読紙し、宇宙科学(space science)や月ロケット実現に必要なテクロノジーの情報などを次々に吸収していきました。
クラークは、19歳でヒューイッシュ・グラマースクールを”無事”卒業すると、経済的事情などを考え、サマセット州教育委員会(Board of Education)の職に就きます。年金部門の監査役の仕事でした。クラーク少年は公務員になったのです。しかしその間にも、クラークは「月」や「宇宙」のことを片時も忘れたことはなく、先端の科学技術や宇宙テクノロジーなどに「月刊英国惑星間協会」などをとおして通じるようになっていったのです。
アーサー・C・クラーク(2):数件隣に住む家の家族から刺激を受けた「空想力」
アーサー・C・クラーク(1)より:
第一次大戦中、母も「モールス信号」を解読する
「電信技手」だった
クラーク家では、父だけでなく、母もまた第一次大戦中は、電気通信の世界に通じていました。母は大戦中、高速で発せられるモールス信号を解読する「電信技手」(技師でなく、”技手”)だったのです。
晩年に亡くなるまで、その技術を忘れることはなかったので、クラーク少年は、母から「モールス信号」の技術や実利的な側面も知らず知らずのうちに体得していたことでしょう。
つまりは、後の衛星通信のアイデアマン「アーサー・C・クラーク」を誕生させたクラーク家の両親はともに、「電気通信の世界」に通じていた人物だったのです。
父か母の一方でも、家庭内においては、その幼少期に父や母の資質や能力、メンタリティにおいて、遺伝因子は別としても、おおいに影響を受けるものですが、父・母ともに同じ特殊世界に通じていたとなるとその影響は甚大なものがあるはずです。
後にアーサー・C・クラーク自身、「電気通信の世界は母の方からも影響があったとおもう」と語っていることからもあきらかです。
数件隣に住む家の家族から刺激を受けた「空想力」、あやしげな本を借りて帰った
しかしアーサー・C・クラークのもう一方のずば抜けた才能、「SF(サイエンス・フィクション)」を物語る「イマジネーション」源はどこからやってきたのでしょう。クラーク本人は、両親のどちらかがSFファンだったとか、密かに得体の知れない文章を書きあらわす隠れた趣味(作家スティーブン・キングの疾走した父のように)があったとかは語っていません。
またよくあるように叔父さんや伯母さん、あるいは親戚や従兄弟からの強い影響があったとも語っていません(様々な小さな影響は幼少期に触れた多くの人からあったようですが、そうした記憶はほとんど薄れていて、ある強烈な契機と影響だけが残ったとクラークは語っている)。
「アーサー・C・クラーク」のずば抜けた想像する能力は、生得のものだったのでしょうか。彼は幼少期から<天才>だったのでしょうか。自由奔放な「想像力」はどこからやってきたのでしょうか。
いくら両親ともども電気通信の世界に通じた人物であったとしても、むしろそうであったならば長男(弟が2人、妹が1人いる)は、将来大人になったら電気通信の仕事か、それに類することを仕事にしようと薄ぼんやりとおもったりする可能性が高いからです。
ところがクラーク少年は、後に「地球はまだ幼年期」にあると大胆に想像してみるようになるのです。そして、まるで無線通信を夜空に向って放ち、「過去」や「未来」の人々と”交信”し、「現在」に生きる世界中の人々を熱狂させる物語を生み出していくのです。
じつはその無限の「空想力」の入口(”発射台”)もまた、生まれ故郷の小さな町マインヘッドにあったのです。それも数件隣の家に。
そこにはエンジニアタイプの両親とはまったくちがうタイプー脇に逸れたインテリタイプの一家が住んでいました。両親も顔見知りだった(だろう)キリーさんの家に、クラーク少年はちょくちょく遊びに行っていたのです。少年時代には、近所の家は、時にまるで別の”惑星”のように感じることもあったでしょう。
そして”周回軌道”のような小径を辿って遊びに行っていた時、その年1928年の11月に創刊されたばかりだった『アメージング・ストーリーズ』誌と”遭遇”したのです。ラリー・キリー氏は(当時30歳位で独身。なんの仕事に就いていたのか、就いていなかったのか、クラーク少年はそのSF雑誌の鮮明な印象しか覚えていないが、当時は年配の紳士という印象だったという)、クラーク少年がこの世で出会った”最初のSFファン”となったのです。
もし近所の一家が、変人とまでいかなくとも風変わりだからということで、子供に接触を禁じた時、あなたは、そして私たちは子供たちから”可能性”を奪うことになりかねません。子供たちはたんに最新テクノロジーが与える”情報”だけでなく、肌で接触し、身体ごとまるごと感得した”体験”を「心の樹」として内面化していくからです。
近隣のお兄さん、お姉さん、お婆さん、お爺さん、叔父さん、伯母さんたちは、子供たちにとって家庭内や学校だけでは成長がいびつになったり疎外される「心の樹」の思わぬ芽吹きを後押ししてくれたり契機となったりしてくれる可能性が大いにあるのです。
なぜなら学校では皆と同じ教科書を与えられ、その暗記力をテストするような方法は、可能性を摘み取ってしまいがちになることです。賢い子供たちのなかには、全課目のテストの点数にもはや重きを置かず、適当なラインで切り上げ、自分の興味の向くことに集中するようになりはじめているようです。
隣近所の人たちとの触れ合いがかつてのようでなくなった昨今、学校と塾だけに子供たちを放り込んでいる家庭は、後に子供たちから大きなしっぺ返しがくるはずです。なぜなら身体だけ大きくなっても、「心の樹」がまったく育っていないからです。
最初の「科学」への関心は、編物機械からやってきた
さて、クラーク少年が、SFファンのラリー・キリー氏以上に多大な影響を受けたのが、彼の”祖母(母ではない)でした。それは「科学」への興味でした。クラーク少年がいつも”オールド”・ミセス・キリーと呼んでいた祖母は、編物機械(ミシン)という1920年代初頭としては小さな家の中に置かれる最高レベルのハイテクマシンでした(日本ではトヨタ自動車の原点である豊田紡績が、自動織機の開発に懸命になったいたのも1920年代初頭でした)。
クラーク少年はその驚きの手動式の編物機械に魅せられ、セーターやストッキングを編み出す”オールド”・ミセス・キリーの横からしこしこ”動力”を供給していたといいます。クラーク少年は彼女にありったけの質問を投げかけました。歯車や針の音におどるようにクラーク少年の「科学」に対する好奇心が膨らんでいったのです。
その一方、SFファンの息子ラリーにも影響を与えたであろう”オールド”・ミセス・キリーだけあって、未知の世界、失われた世界のことに興味をもっていた女性でした。たとえばアトラティス大陸の存在などをずっと真じていたのも彼女の影響でした(『アトランティスー大洪水以前の世界』(1882 イグナチウス・ドネリー著)といった類の本をクラーク少年に貸し与えていた)。そしてちょうどこの頃(11歳頃)のことです。クラーク少年はあがったばかりのグラマースクールの地下の溜まり場で、未知なるもの、そして「未来」や「科学」への関心を、さらに決定的なものにするものを見つけるのです。それはクラーク少年の「マインド・ツリー(心の樹)」の”樹根”の芯につながり、さらに頑丈な芯を形成するものとなっていくものでした。
アーサー・C・クラーク(3)へ続く:
アーサー・C・クラーク(1):母は「モールス信号」解読の「電信技手」
<strong>アーサー・C・クラークの「マインド・ツリー(心の樹)」(1)- 父はかつて郵便局に務める「電気通信」技師、母も「モールス信号」解読の「電信技手」だった </strong>
はじめに:
奔放な「イマジネーション」と、
リアルな「サイエンス・ファクト」の地平線
映画『2001年:宇宙の旅』(スタンリー・キューブリック監督)の共同原作者であり、20世紀の「SF(サイエンス・フィクション)作家」を代表するひとりアーサー・C・クラークは、一方で人工衛星を使った電気通信リレーや軌道エレベーターなど実際的な科学的なアイデアマンとして、また宇宙開発に関する科学解説書の作者としても広く知られています。
「衛星通信」に利用されている赤道上空3万6000キロにある静止軌道は、「クラーク軌道」と呼称され、SF小説に描かれた物語は科学技術に裏打ちされたまさに近未来の科学システムを先取りしたものでした。
他の大勢のSF作家と異なるアーサー・C・クラークSFのおおきな特徴は、壮大な「人類の宇宙的進化」を主要なテーマにしたことで、そのためにはリアルな科学的知識は必要不可欠だったのです。そのために人類の未来を扱う科学解説者としても活躍できたのです。
アーサー・C・クラークのこうした奔放な軌道をえがく「イマジネーション」と、その軌道上に打ち上げる実際的な「科学的知識」はいったいどこからやってきたのでしょう。日本の中学・高校にあたるグラマースクールを卒業した後、クラークは大学に行くことができず、公務員になっています。
州の教育に関する事務を担う教育委員会の年金部門の監査役でした。第二次大戦中は、英国空軍の将校となり、レーダーや電波探知法の開発もおこない、戦後(28歳頃)にようやくロンドン大学キングス・カレッジ校に入学し物理学と数学を学んでいます。
では奔放な「想像力」はどこで鍛えられたか、またその「想像力」と科学的知識はどこでどの段階で、クラーク少年の「マインド・ツリー(心の樹)」のうちで連結されたのでしょう。またどんな”軌道”を描いて、「アーサー・C・クラーク」が誕生したのか。まずはクラーク少年の生まれ育ったイギリス南西部の入り江に面した小さな町をのぞいてみましょう。
なんにせよそこが「アーサー・C・クラーク」の「マインド・ツリー」がまぎれもなく育った”土壌”であり、未来の「楽園の泉」を幻視した場所なのですから。
中世の面影を残した英国サマセット州の美しい海岸線のある町に生まれる
アーサー・C・クラーク(Sir Arthur Charles Clarke)は、1917年12月16日、イギリスの南西部に位置し、ブリストル海峡の南側につながる海岸線をもつサマセット(Somerset)州のマインヘッドに生まれています。
マインヘッドは14世紀に小さな港をその嚆矢とし、中世に地域の交易センターとして発展した古い歴史のある町です。現在も人口1万人程のマインヘッド(Minehead)は、エドワード朝時代の古い建築物が残る、なんら未来的なものが存在しない海岸線に沿った静かで小さな町です。
1世紀程前に隣町に暮らしていたロマン派詩人サミュエル・テイラー・コールリッジが、親友となった詩人ウィリアム・ワーズワースとよく散策したマインヘッドに連なるブリストル海峡を見晴らせるなだらかな丘陵がありますが、彼らが詠ったのも中世の面影を残す景色でした(2人で英国ロマン主義運動の画期となる『抒情詩集』を著した)。
また「湖水詩人」とも呼ばれる2人が一緒に滞在していただけあって見事な入り江がある。アーサー・C・クラークが後にスリランカに暮らすようになった理由の一つが、美しい海や湖水の存在であったにちがいない)。
イギリスの他の地域と比べても、その中世的風景をのぞけばなんのとりえもなさそうな小さな町の環境から、どのように20世紀を代表するSF作家であり、今日の衛星通信の基幹となる「衛星通信」の科学的方法をすら”発見(『Wireless World』誌に論文発表)”した人物が生まれえたのでしょうか(ちなみにアーサー・C・クラークは、11歳の時からグラマースクールに通い、卒業すると公務員になっています。「衛星通信」ともなれば当然すすんだ理科系のある大学にすすんだとおもうでしょうが、アーサー・C・クラークは当時大学に行くことはできませんでした)。
海に囲まれた日本の多くの地域でも、歴史は少なからずあるけれども先進的な産業や科学文化がほとんどないマインヘッドのような村や町はいたるところにあるとおもいます。ある意味、大都会にふつうにあるものが欠如しているぶん、「想像力」を鳥のように羽搏かせるにはうってつけの土地といっていいかもしれません。
大都会のロンドンやマンチェスターと比べ、日々満天の星を眺めることができ、大海に通じる海峡と海風、自転する「地球」の呼吸を肌で感じうるような場所だったとおもわれます。なんといっても「海」は、宇宙の<鏡像>なのです。アーサー・C・クラーク自身、30歳を越えた頃に潜水をはじめたのも、「宇宙探査」への興味からだったのです。
父はかつて郵便局に務める「電気通信」技師だった
さて、先進的な産業や科学文化がまったく乏しい小さな町マインヘッドでしたが、そこには存在したのはアーサー・C・クラークの「父」となり「母」となる、第一次大戦中に懸命に生き抜いている悩み大き”ひと”でした(アーサー・C・クラークは、第一次大戦中に生まれている)。アーサー・C・クラークといえど、後に著した『幼年期の終わり』に登場する全能の神の如き存在のオーバーロードや、地球人を超えた知能をもつオーバーマインドから、命や知性を頂いたわけもありません。
小さな海辺の町の小さな家に暮らしていた「父」は、郵便局に務める「電気通信」技師でした。第一次世界大戦終結後に(戦中は「電気通信」技師としての技能を提供させられたにちがいありません)、復員士官となった父は、他の復員士官たちと同様にどうやら一方的に農場をあてがわれ農業をやらされていたようです。
その場所がマインヘッドでした(クラーク家の先祖がどこの出身かは分かりませんが、まだ戦時中のマインヘッドで誕生しているので少なくともこの地に縁もゆかりもあるはずです)。
郵便局勤めの、いち技師が素質も経験もない農業をたやすくおこせるわけがありませんでした。商売感覚もまるでない父は他に手に職をもつこともないまま、鬱屈しながらもせっせと農場を営んでいたといいます。そしてクラークが14歳の時(1931年)に若くして亡くなります。
クラークは大戦が終焉する1年前に生まれているので、「電気通信」技師をしていた頃の父の姿から直接的に影響を受けることはなかったようです。
けれども自伝の『楽園の日々ーAstounding Days』(1990年 早川書房)には、「電気通信という父親の経歴が、わたしの将来の進路に影響したのではないかと、ときに思ったものである」と語っているところをみると、少年時代にクラークは父がかつて電気通信技師だったことをちゃんと知っていたに違いありません。
アーサー・C・クラーク(2)へ続く:
この第一次世界大戦ではじめて人類は、戦車やマシンガン、戦闘機といったお馴染みのハードウエアだけでなく、電話や無線電信(Wireless Communication)を戦場で用いはじめています。しかし志願して陸軍飛行連隊に所属したサン=テグジュペリが第一次大戦後、非戦争時になると目指していた軍用機操縦士としての当てあてがなくなり、民間機によるアフリカやアルゼンチンへの危険極まりなり郵便配達が仕事となったように、「電気通信」技師だった父も、そのまま能力を活かせる職場に復帰できませんでした。疲弊した経済社会が回復し、戦場で活躍していたテクノロジーが民生化されるまでには相当の時間がかかったのです。
ジャック・ケルアック(4):プロのアメフト選手になろうと夢見る
ジャック・ケルアック(3)から:
15歳の時、父の印刷所が破産。家族から働きに出るよう懇願される。作家への夢、諦める
14歳の時(1936年)、父の印刷所「Spotlight Print」が、氾濫したメリマック川に飲み込まれてしまいます。川の氾濫の補償は無く、社会や政府に対する不満を蓄積させた父は、鬱憤をはらすように酒をあび、翌年、ついに父の印刷ビジネスは完全に破産してしまいます。
雇われ印刷工として働いていたものの、もはや一家の家計も破綻寸前、父は息子ジャックに物を書くことを辞め、製粉所で仕事を探して欲しいと懇願したのです。ケルアックはサロウヤンとヘミングウェイを理想に、文章力をつけようとしていた矢先だったこともあり、大きなショックを受けます。
母は、ジャックにゆくゆくは大学に行くようにと諭しましたが、作家やアーティストの道に入ることは承知しませんでした。将来のことを励ましながらも、とにかく仕事を考えて欲しいと告げたのです。こうして15歳の時、少年ケルアックは、家の経済的事情から、作家(writer)になることを諦めています。
ヘミングウェイやゲーテ、H.G.ウェルズやウィリアム・サロウヤンといった一流作家になる「夢」はもちろん、三文小説や探偵小説の作家になることもこのとき諦めたといいます(母は再び靴工場で皮はぎをはじめ、父は印刷屋に就職し、一家は苦境を乗り越えようとしましたが、ケルアックは家計の状況から、近い将来大学の学費は無理だろうと、察していたという)。
「スポーツ」への熱中。プロのアメフト選手になろうと夢見る
10代半ば、ケルアックが夢中になっていたのは、「小説」だけではありませんでした。もともと短距離走に秀でたケルアックは「スポーツ」にも熱中しはじめていました。逞しい筋肉質の身体はアメリカンフットボール向きで、俊敏さとタックル力は中学生ばなれと噂され、中学後半にはハイスクールのチームに誘われプレイしていたほどでした。
入学したハイスクールでは小説家になることを諦めたからには、プロのアメフト選手になろうと夢み、真剣に練習に取り組んでいます(野球の試合もよくしたが、野球に関してはケルアック自身の考案によるカードをもちい、8チームによるシーズン全154試合の全試合を記録し続けた「野球ゲーム」が、生涯にわたった趣味だった)。
しかし、ケルアックはいつも指導者と衝突してしまうのです。諦めた作家への夢、アメフト選手への道で繰り返される衝突。少年ケルアックはジレンマに陥ります。
そんな時、足が向うのは図書館でした。ゲーテ、ヴィクトル・ユーゴー、エミリー・ディッキンソンと、再びケルアックは読書にはまり込んでいったのです。座右の書は、『ブリタニカ国際大百科事典』だったといいます。また映画の魅力にも取り憑かれ映画館にも足繁く通っています。
父が映画のポスターやプログラムを印刷していたこともあり、タダで入場できたのです(姉のニンとかなり小さな頃から二人して映画館に通っていた。映画館でのアトラクションに出演していた喜劇俳優W.C.フィールズやマルクス・ブラザーズを、少年ケルアックは直に見ている。映画を通してニューヨークに憧れをもつようになる。ニューヨークに出てからは労働者階級のヒーロー、ジャン・ギャバンがケルアックのヒーローに)。
それまで異性に対しては奥手だったケルアックでしたが、女性たちは美男子ケルアックの虜になっていきます。16歳の時、ノスタルジックにすらおもえる恋愛をし、翌年別の女性とも付き合いだします(一生涯、ケルアックは複数の女性や、時に男性の間を彷徨うことになる。
ニューヨークの私立高校時代、学校新聞や学校の文芸誌に小説を発表する
なんとかハイスクールに通えたものの突破口が見つからなかったケルアックでしたが、得意だったスポーツが扉をあけることになります。同16歳(1938年)の時に出場した試合で連続して大活躍、その存在はボストン大学やてニューヨークにあるコロンビア大学のアメフトチームのスカウトマンにまで知れ渡ることになったのです(実際、ボストン大学のスカウトから父の印刷会社を通してはたらきかけがあった)。
その結果、大学に行くための唯一の手段だった奨学金が確実なものとなったのです(両親にとってアメフト選手は大学へ入るためのきっかけに過ぎず、将来は保険会社のエリートサラリーマンになることを望んでいたという)。そしコロンビア大学のアメフトの有名コーチだったルー・リトルの知るところとなったのです。
ニューヨークの名門私立高校ホレスマンでの大学入学前の補修コースに通っている間、ケルアックはジャズ、映画、ストリート、セックスとニューヨークそのものと”交合”していきます。またホレスマン校の学校新聞や学校の文芸誌に小説を発表していきました(この高校にはコロンビア大学のアメフトの下部チームに相当するチームがあり、ケルアックはそこに参加していた)。
この時期、ジャズへの関心は一気に深まり、学校新聞のインタビュアーとしてグレン・ミラーにインタビューしたり、生涯レスペクトしつづけるレスター・ヤング(カウント・ベイシー楽団のテナーサックス奏者)を聞きまくっています。このジャズがケルアック流「執筆」の”リズム”となっていくのです。
コロンビア大学の入学が決定的になったケルアックが一時帰郷すると、地元新聞は「ローカルヒーロー」としてケルアックを迎えます。ケルアックはその後も生涯にわたってことあるごとに、故郷ローウェルに帰郷しています。故郷ローウェルは何度もケルアック作品の舞台として登場することになりますす(第一作品『街と都会』から、『ドクター・サックス』『マギー・キャシディ』『ジェラールの幻想』の自伝的4作品がローウェルを舞台にしている)。
故郷ローウェルは、ケルアックの「マインド・ツリー(心の樹)」の”樹芯”にある土地であり、”奇妙で憂鬱”な町だとつぶやきながらも、自身の”心根”が深く強く張り巡らされた場所だったのです。
ケルアックにとって、子供時代は記憶の中で何度も”帰郷”する場所であり、時間でした。『ドクター・サックス』では、”子供時代最期の日々”を描き、『ジェラールの幻想』ではケルアックが4歳の時に亡くなった兄を記憶の果てまで追想し、『街と都会』では故郷ローウェルの幼友達のキャラクターを使って、ローウェルに大ファミリーを創りだしたのでした。
大学入学前、ジャック・ロンドンについての「伝記」を読み、冒険・旅人に魅了される
スポーツ選手として奨学金対象になったものの、ケルアックの気持ちはプロのアメフト選手ばかりにフォーカスされていなかったようです。さすがに両親には告げることはなかったものの、戦死した若き詩人セバスチャン・サンパスの影響まぬがれがたく、「17歳の時、作家になろうと心に決めた」とケルアックは記しています(『孤独な旅人』:著者序文)。
そして大学入学前の地元ローウェルでの休暇中、ケルアックは強烈な刺激と大きな影響を受けることになる作家に出くわしています。ジャック・ロンドンでした。ケルアックはジャック・ロンドンの小説だけでなく、ジャック・ロンドンについての「伝記」を読み、深く魅了されています。冒険、そして<孤独な旅人Lonesome Traveler>への思いが止み難くなります。
ちょうどこの頃、図書館司書ミス・マンスフィールドが主宰する読書会「三文文士会」のメンバーだった大学生サミー・サンパスが、ケルアックに社会主義やオズワルド・シュペングラー、ウィリアム・サロイヤン、トマス・ウルフ(『クール・クールLSD交感テスト』や『虚栄の篝火』『ライトスタッフ』の著者で、ニュージャーナリズムの旗手トム・ウルフではない)を教えています。
『天使よ、故郷を振り返れ』や『時と川について』などを書いた自伝的作家トマス・ウルフの作品を通し、ケルアックの「Mind Tree(心の樹)」に、故郷ローウェルなみならず、「アメリカ」が<一篇の詩>として映り込んできたのは、大学入学後、アイビーリーグ対抗戦で脚を骨折し、思わぬ状況にひとり読書を深めていったときでした。
ジャック・ケルアック(3):自らつくった「新聞」を発行
小学校時代についた渾名は「メモリーベイブ(記憶の天才)」。11歳「日記」を書きだし、自らつくった「新聞」を発行。15歳、父の印刷所が破産。作家への夢、諦める。アメフトに熱中
ジャック・ケルアック(2)からの続き:
小学校時代についた渾名は、「メモリーベイブ(記憶の天才)」
6歳の時、ジャックは、教会付属の聖ルイと聖ヨセフ校というキリスト教系の小学校に通っています。教会付属の両小学校ではバイリンガル教育が行われていました。午前中は英語で主要科目が講義され、午後はフランス語でフランスの文化と歴史が教えられていたのです(ジャックは『聖書』もフランス語で初めて読んでいる)。
ジャックは家庭で話されるフランス語に愛着を感じすぎていて、英語で話すときは言葉が完全に分からないこともあり言葉少なになったといいます。聡明だったにも拘らず早逝し、なかば神格化されていた兄ジェラールと比べれば、ジャックは目立たぬ存在だったといいます。しかしじょじょにジャックは、皆の注目を集めはじめはじめるのです。
ついた渾名(あだな)は、「メモリーベイブ」つまり、「記憶の天才」でした。ジャックは、見聞きした言葉や出来事を誰しもが驚くほどに記憶することができたのです。家族やいつも一緒にいる友人たちは早くから気づいていたといいます。
ジャックは、幼少期からひとりで空想にふけることがよくありました。その空想のなかでスポーツの新しいルールをつくったり、一人で大リーグの試合を戦ったり、さまざまな物語をつくっていたといいます。
またインクの匂いのする父の仕事場に行っては、印刷用のキーボードで遊んだりしていました。後の「打鍵の達人」とも「数百万語の男」とも呼ばれることになるケラワックは、この頃のキーボード遊びの早業からきているようです(手書きの原稿やメモをタイプするときに、思考と連動した驚くべきスピードで文字を打つことができた)。
書いたショート・ストーリーを女性の図書館司書に読んでもらった
公立中学のバートレットスクールに入学する11、12歳頃には、友達と同様にコミック少年になっていました。皆で挿絵入り週刊誌の発売日の木曜を心待ちにしていたといいます。少年ケラワックは、掲載コミックの「ザ・シャドウ」(TV化、ラジオ・ドラマ化、映画化された最大級のパルプ・マガジン・ヒーロー)や「グリーン・ホーネット」(武道のマスターでアジア人助手カトーとともに悪と闘う)、「幽霊探偵」の大ファンでした。
「シャドウ」の主人公ラモント・クランストンに夢中で、黒いマントをはおり裏通りでショウドウごっこをして遊んでいたようです(その光景はローウェルを舞台にし、幼少期を描いた自伝的小説『ドクター・サックス』に描かれた)。
その一方で、「シャドウ」の作者、ウォルター・ギブソンが毎週30万語執筆することを知って、そのスピードと生産力に刺激を受け、コミックを基に時自分なりの「物語」を書きはじめていました。それを父の印刷工場に持ち込んで、リノタイプ印刷しています。
バートレットスクールに入学した年の秋(ケルアックは3月生まれなのでその時点では12歳になっていた)、少年ケルアックは図書館司書ミス・マンスフィールドと知り合い、文学にさらに触れ、幾つか書いていたショート・ストーリーを学校の外でミス・マンスフィールドに渡して読んでもらうようになります(後にジャック・ケルアックのトレードマークにもなるノートブックに走り書きしたものだったようです)。
その一編が、「Jack Kerouac explores the Merrimack」と題された短篇でした。 「ジャック・ケルアックが、メリマック地方を探検する」というものだったのです(『孤独な旅人』にある著者の序文には、初めて小説を書いたのは11歳の時とある。同じくマサチュセッツ州生まれのデビッド・ソローが1849年に自費出版した処女作の題名は、『コンコード川とメリマック川の一週間』だった)。
「メリマック地方」は、ローウェルの北方、メリマック川の上流にある町ナシュアもおそらく含まれたはずです。前述したようにナシュアはジャックの祖父の大工ジャン・バティスト・ケルアックが辿りついた土地であり(自らの腕で家を建てている)、母ガブリエルも育った場でもあったのです。ほとんど最初に書いた短篇にして、父のように「自己」にスポットライトをあて、自分が「探検、体験したこと」を書いていたのです。しかも<ケルアック家の源流>を探索するかのような「ロンサム・トラベラー(孤独な旅人)」となって。
11歳、「日記」を書きだし、自らつくった「新聞」を発行
この年(11歳の時)、コミック少年だったケルアックは、「日記」を書きはじめています。さらに自分で考案した競馬とフットボールの試合についての記事を自ら書き(ケルアックは以前から空想のなかでスポーツの新しいルールをつくって、ひとり物語っていた)、それを自らつくった「新聞」に載せて「発行」したのです。
「メモリーベイブ」と渾名されていた少年ケルアックの「マインド・ツリー(心の樹)」が、一気に樹勢を高めたのが、公立中学にちょうど入学した年からだったといえるでしょう。
少年ケルアックの短篇を読んだ図書館司書ミス・マンスフィールドは、ものを書く才能があるわねと、ケルアックを激励し勇気づけています。英語が依然負い目だった少年ケルアックは、生来の内気さもあり、クラスでは周りと距離ができるほど静かな少年だったようです。友達も少なく、お高くとまっている優等生として周りからみられていたようです。
そんな控え目な少年の裡に、担任女性教師ミセス・ディネーンもまた、物書きとしての天分に気づき励ましています(宿題の提出物が中学生レベルをはるかに超えていた)。この頃から、少年ケルアックにとって週一回、図書館から本を借りるのが「行事」のようになっていました。
しかしケルアックは授業をさぼることに抵抗感はなく、自室や友達の部屋でラジオ放送局920クラブを聴きまくっています。流れてきたのは、トミー・ドーシー楽団、フランク・シナトラがメインボーカルをとっていたグレン・ミラーのビッグバンド、バディー・リッチやジーン・クルーパのジャズでした。
ケルアックの「リズム」への関心の嚆矢で、旅の友にいつもボンゴを持ち歩くようになったのもこの時の影響からでした。クラスでは小さくなっていましたが、外では頭角をあらわしだし小さなグループのリーダーになっていきます。
ジャック・ケルアック(4)へ続く:











![マイケル・ジャクソン~真実のマイケル・ジャクソン [DVD] マイケル・ジャクソン~真実のマイケル・ジャクソン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51JnFNc07kL._SL500_.jpg)



![映画ポスター MICHAEL JACKSON マイケルジャクソン (追悼10周年) - (絶版)This Is It(40x60)[並行輸入品] 映画ポスター MICHAEL JACKSON マイケルジャクソン (追悼10周年) - (絶版)This Is It(40x60)[並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ziqo8gZwL._SL500_.jpg)