ジャック・ケルアック(2):慕っていた4歳年上の兄の死と家族の困難
町のコミュニティーも、ケルアック家の日常語はフランス語だった
ローウェルの町では、フレンチ・カナディアン(フランス系カナダ人)は、植民した18世紀からこのかたニューイングランドの支配者たちから疎まれていたといいます。その結果、フレンチ・カナディアンは、自分たちをあたかも”ゲットー”のように内に組織化し(カトリック教徒だった)、先祖伝来の言語や文化、宗教を死守しようと、英語を日常言語とする町の隣人たちとは深く交わらないできました。
実際、ケルアック家の日常言語も「フランス語」で(実際には父レオはある程度、英語を話すことができたが、母は一切喋れなかった)、ケルアックが英語を難なく使いこなせるようになったのは、ハイスクールの最終学年から大学初年度の頃でした。
当時フランス人コミュニティーで成り立っていたローウェルの町では、ジュアール(joual)と呼ばれるカナダ系フランス語が日常語とされ、英語はほとんど日常会話にもちいられることはありませんでした(ジュアールは相当の方言化しはじめていたようで、後にケルアックがカナダのケベック州のモントリオールやパリに旅した折り、ジュアールの話し言葉ではしっかり通じなかったといいます)。
こうした言語環境も、「Love, Work, and Suffer」をモットーとするケルアック家の人々が(ジャック自身も含め)先祖たちの「物語」を強く”意識”しないではいられなかった要因の一つだったはずです。
ケルアックの母ガブリエルの祖母(Gabrielle L'Evesque)もまた半分インディアンの血が入っていました。L'Evesqueというフランス系の男と結婚し、インディアンのように(そしてジャックのように)頬骨が少し高い黒髪の子供をもうけています。
ガブリエルもまたカトリック教徒のフレンチ・カナディアンでフランス語が日常語で、ローウェルの少し北に位置するニューハンプシャー州ナシュア(Nashua)の町で育っています(生まれはカナダのケベック)。
ナシュアはジャックの祖父で大工だったジャン・バティスト・ケルアック(Jean-Baptiste Kerouac)が辿りつき、自らの腕ひとつで家を建て暮らした町でした。
ナシュアの製粉工場で働いたのち酒場のオーナーとなっていた父が38歳で亡くなったため<(母は早くに亡くなっていた)、ガブリエルは14歳の時から孤児になっていました。レオ・ケルアックと出会った時は、靴屋で働いていたといいます。靴工場で皮はぎ女工だった時もあったようです。
父レオは、ライター兼活字打ちとして地元のフランス語新聞社で働いていた
ジャック・ケルアックの父レオ・ケルアックは、保守的な労働者で、短気で、喧嘩早く、大酒飲みで(ジャック・ケルアックも後にアルコール依存症になる)、印刷所を家業にしていて、川の氾濫で印刷所を亡くしてから(1936年)、社会への不満を増大させ、社会の枠から飛び出すことを夢見るようになり、競馬場のパドックの常連だった、と紹介されています(イヴ・ビュアン著『ケルアック』ガリマール新評伝シリーズ 祥伝社)。
ところがレオ・ケルアックの青年時代をみると、ずいぶんイメージが変わってくるのです。伝記『Jack Kerouac - a Biography』の著者マイケル・ディットマンによれば、父レオ・ケルアックは学生時代、レオの父ジャン・バティスト(ジャックの父方の祖父)の勧めで、ニューヨークのロードアイランドにある私立学校に通い、ライター(物書き)とプリンター(印刷工)の腕と技術を磨いています。ハンサムだったので女性にすごくもてた(a ladies' man)ようです。
卒業するとレオは、ローウェルに戻りフランス語新聞社「L'Etoile」で、レポーター兼活字打ち(typesetter)として働きだしています(「マインド・ツリー」的に興味深いことに、ジャック・ケルアックも若い時期、ほんの数ヶ月だけでしたが、地元のローカル紙「the Lowell Sun」でスポーツ記者として働いている)。
ところが「L'Etoile」から冷たく扱われるようになり同社を去り、ダウンタウンの運河沿いにあるコロニアル調の旧いビルの空き部屋を借り、自ら小さな印刷会社「Spotlight Print」を立ち上げるのです。「Spotlight Print」という社名にも、つねにスポットライトがあたっていないと気がすまない性格の一端があらわれているようです。
この「Spotlight Print」で、レオ・ケルアックがはじめたのは、地元の劇場とバーレクス・ハウスの演目のプログラムやポスターや貼り紙の製作と印刷だけでなく、「Spotlight」というエンターテインメント紙の企画・編集・製作でした。ジャック・ケルアックの父レオ・ケルアックは、単なる小さな町の印刷工でもなければ、喧嘩早く大酒飲みで、競馬好きの根っからのギャンブラー体質だけで片付けられる人物ではなかったようです。
しかしかなり変わり者だったことだけは確かなようで、本業以外にも、ソーシャルクラブを主宰したり、スポーツクラブをつくる計画も立てたり、運転もできないのに新車のビュイックを購入したりしています(元レスラーで従業員だった者に家族で旅行する際にドライバーに用立てていた。ジャック・ケルアック自身も小説には描くものの30代半ばまで車の運転方法は、父と同様に学んだことがなく、亡くなるまで運転免許証は持っていなかった)。
しかし、そうした企てはことごとくうまくいかなかったようです。さらには市議会選挙に出ようとしたり(悪評が不利と諭され断念)、競馬場のパドックで顔を見せない日はなかったようです(アメリカ中の競馬場を渡り歩き、勝ち馬を当てて生計を立てるぞ、と言い張った。後に、ジャックも盟友ニール・キャサディともに競馬熱に取り憑かれることに)。
慕っていた4歳年上の兄の死と家族の困難
ケルアック家の長男ジェラール(ジャックより4歳年上。他に姉キャロリーヌがいる)は、赤ん坊の頃に連鎖球菌に感染し、ブイヨー病(激しい痛みを伴うリウマチの一種、心不全や呼吸不全をもたらす)に罹っていました。
この時期、まだ「Spotlight Print」を経営していた父レオは、家族の困難をうまく乗り越えることができず、浮気に走ったりしたため(ガブリエルは夫レオは同性愛者じゃないかと疑っていた)、ケルアック夫妻はつねにひと突きあれば崩壊するような関係がつづいていたといいます。
聡明だった長男ジェラールは元気な時は小学校にも通学でき、絵も得意で弟ジャックに絵を教え(ジャック・ケラワックは生涯、絵を描きつづけている)、そんな兄をジャックは幼い頃から偶像視していたといいます(後に作品『ジェラールの幻想』となる。またケルアックがつねに尊敬できる男性を無意識の内にも求めていたのは、憧れだった亡くなった兄の存在を無視することはできない)。
ジャック4歳の時、兄ジェラール(小学校2年生の時)、亡くなります。4歳の時のことでしたが、兄の死はジャックの生涯に大きな影響を与えることになります(夜になると恐怖に襲われ、暗闇を恐れるようになったジャックは兄の写真の前で祈り助けを求めた)。
また愛情を注いでいた母への衝撃も大きく、ジェラールの死後、母は再び靴屋で働くようになっています。その一方、父レオの方はボクシング・ジムを開いています。面倒をみていたボクサーがダメとなると、その男を今度はプロレスラーに仕立てあげてるのでした。結局ボクシング・ジムは破産、レオは再び印刷工の職を探したりしています。
父レオの絶えざる変わった行動は、ある種ゲットーのようなローウェルのコミュニティーを超え出るものを探す”旅”でもあったようです。
ジャック・ケルアック(3)に続く:
ジャック・ケルアック(1):ケルアック家の「ファミリー・サガ(家族の物語)」
若い頃、父から聞かされたケルアック家の「ファミリー・サガ(家族の物語)」。印刷会社を経営していた父は、かつて地元のフランス語新聞社でライター兼活字打ちとして働いていた。
フレンチ・カナディアンとして幼い頃から親しんだフランス語でインタビューを受けているケルアック
はじめに:
若い頃、父から聞かされたケルアック家の「ファミリー・サガ(家族の物語)」
2007年、「ヒッピーの聖典』と化した自伝的小説『オン・ザ・ロード(路上にて)』が、当初英語ではなくケベック・フレンチ語で書きはじめられていたことが発見されました。
ジャック・ケルアックは、日本語ウィキペディアでは米国人、英語版ウィキペディアではカナディアン・アメリカン(カナダ系アメリカ人)ですが、ケルアック一家や故郷のマサチューセッツ州ローウェルの町ではフレンチ・カナディアン(フランス系カナダ人)と意識していたことを考え合わせると、再び『オン・ザ・ロード』や「ジャック・ケルアック」への興味がつのってきます。
ジャック・ケルアックが生み出した数多くの小説の多くは、若い頃に父から聞かされたケルアック家の「ファミリー・サガ(家族の物語)」への強烈な”反応”から産み落とされたものだったともいわれています。『孤独な旅人(Lonesome Traveler)』で描いたのは、自身のルーツがケルト語を話すフランス・ブルターニュ地方の出身だったケルアック家の放浪譚でした。
またジャズ、旅、ドラッグ、カトリック・スピリチュアリティ、ブディズム(仏教)など、内面世界へののめりは、ケルアックの場合つねに移動をともない、それが初期には『On the Road』となり<(26歳の時に書きはじめている)、「カウンターカルチャー」の源流の一つとなり、社会の枠を越え、移動し、熱く共振する「ビート・ジェネレーション」ケルアックが生み出した言葉)世代を魁けていったのでした。
「カウンターカルチャー」の源流を生み出すことになったジャック・ケルアックは、どんな人物だったのでしょうか。生まれ故郷ローウェルで英語も教えられないまま育てられ、早逝した兄と比べ、まったく目立たなかった一人の少年が、どのように「数百万語の男」と呼ばれるまでになったのでしょう。
フレンチ・カナディアンのコミュニティで、母の愛情たっぷりに育てられた少年が、どんな経緯から長期に渡る放浪的な「旅」に誘われるようになったのでしょうか。
ウィリアム・バロウズやアレン・ギンズバーグ、ニール・キャサディらとの出会いと交流が、ジャック・ケルアックをさらに刺激してゆき、また逆に彼等を刺激してゆきます。
そしてアメリカン・フットボールの一流プレイヤーになれると推薦を受けコロンビア大学に入学したジャック・ケルアック。第二次大戦中、商船に乗り込み、8日だけ海軍に入隊し、精神に異常があるとして除隊命令されたジャック・ケルアックもまた存在します。
故郷ローウェルの町は、つねにケルアックの拠り所であり、”根っ子”であり続けました。いったいジャック・ケルアックの作品と魂の<根底>には何があったのでしょう。では一緒に、『On the Road』の先にある、ジャック・ケルアックの「マインド・ツリー(心の樹)」へ向ってみましょう。
ケルアックは一族から「祖先」の話や「家系」のことをよく聞かされていた
ジャック・ケルアック(Jack Kerouac : 本名:Jean Louis Kerouac )は、1922年3月12日(〜1969年)に、米国北東部のマサチューセッツ州ミドルセックス郡ローウェルで生まれました。ローウェルは、ボストンから内陸へ北西約45キロ(車で約1時間)に位置する、メリマック河畔にひろがったマサチューセッツ州5番目に大きな町です(人口約10万人)。
1820年代より南部で生産された大量の綿が運び込まれる繊維工業のセンターとなったため、フランス系カナダ人、アイルランド人、ギリシャ人、ポーランド人、ポルトガル人ら、多くの移民や出稼ぎ労働者が流れ込んで形成された町です。
繊維工場で働く独身の女性はミル・ガール(Mill Girl:女工)として知られ、町の名前もアメリカの繊維産業に革命を起こしたことで知られるフランシス・ローウェルからとられ、彼は女性をはじめて工場で働かせたパイオニアでした(ニューイングランド地方の農場出身の15歳〜35歳までの女性だった。男性よりも低賃金だったが宿泊施設、教育面など厚く待遇しローウェル・システムとして知られる)。
ローウェルの町からメリマック川に沿ってわずか10キロ程行くと、ニューハンプシャー州ですが、ローウェルがあるマサチューセッツ州を含め米国北東部の6州は、ピリグリムファーザース(イギリス国教会から分離を求める清教徒分離派グループ)が入植した土地でもあり、米国で”白人にとって”最も歴史に満ちたエリアです。
そしてこの”歴史の森、川、そして道”につながる場所に生まれたことは、少年ケルアックの将来への道(on the Road)に扉を開けたのです。その扉の最初のひと押しをしたのは、ケルアックの両親と叔父さんたち、叔母さんで、彼等は少年ケルアックに「祖先」の話や「家系」のことを話して聞かせたのでした。
そのなかには先祖の一人が北極近辺まで行ってサバイブしたというような「噂話」も混じっていましたが、多分に「伝説」も含まれ、少年ケルアックの「空想」を逞(たくま)しくしていったようです。
イロコイ族などインディアンの血が入っている話をよく両親や親族から伝えられていた
少年ケルアックが、父から何度となく聞かされた祖先の話は次のようでした。最初に米国にやって来た祖先は、a Breton baron from Cornwell named "Louis Alexandre Lebris de Kerouac"、つまりルイ・アレクサンダー・ルブリ・ド・ケルアックは、イギリス南西部のコーンウォール(ケルト系の言語コーンウォール語を語る独自の文化がある地域、Land's Endーランズエンド岬ー「地の果て」の象徴とも言われる場所として知られる)から、フランスのブルターニュ地方に向った貴族だと。
ゆえに自分たちはニューイングランドの支配者アングロ・サクソンではなく、ケルトの血脈につながっているんだと。晩年の40歳頃(ケルアックは47歳で亡くなっている)</span>にも、ケルアック一族は、『トリスタンとイゾルデ』(シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』の源流)といったケルトの説話があるアイルランドにまで遡ることができると信じ、父と同様「 Kerouac」の語源をあれこれ探求していました。
その後、ケルアックはフランスに行き、その先祖(a Breton baron from Cornwell )を調査しています。その結果、父から聞かされていた人物は貴族などではなく、植民地時代の商人(Maurice-Louis-Alexandre Le Brice De Kerouack)だったことを突き止めています。
ケルアック家に伝わる先祖の話によれば、ルイ・アレクサンダー・ルブリ・ド・ケルアックは、1750年に大西洋を渡り新大陸に入植し、イギリスの入植者と闘争を繰り広げながら、カナダの東部ケベック州の the Rivire du Loup に土地を与えられ、その子孫は北米インディアンのモホーク(Mohawk)族とコグナウォガ(Caughnawaga)族の血の入った女性を娶(めと)り、ポテト農場を営みだしています。またイロコイ族がケルアック家の「ファミリー・ツリー」に存在したことも告げていました。
先祖は大西洋を渡ってきた辺境の人物だったこと、ケルアック家にそして自分の遺伝子にインディアンの血が流れていることは少年ケルアックの「マインド・ツリー(心の樹)」に深く刻みこまれるのです。そうした認識はケルアックのアイデンティティをゆさぶり、つねに大きな影響を与えていったようです。20歳の時に書きあげた最初の長編小説『The Sea is my Brother(海は我が兄弟)』にもそれは木霊(こだま)しています。
また、アイデンティティのゆらぎからもまれたスピリットは、ローウェルのコミュニティにも近代国家の体制の枠には収まりきらない、”コスミック・ビート”を放ちはじめることになるのです。
ジャック・ケルアック(2)に続く:
・参考書籍『Jack Kerouac a Biography』by Tom Clark,Marlowe & Company New York 1984/ 『Jack Kerouac a Biography』by Michael J. Dittman Greenwood Press 2004 / 『ケルアック』イヴ・ビュアン著 ガリマール新評伝シリーズ 2010 祥伝社
竹久夢二(1):「夢二ワールド」の根源になった生まれ故郷
「夢二ワールド」の根源になった郷土。3歳の頃から馬の「絵」を描きだす。大好きだった6歳年上の姉。「写生」に革新をもたらした担任の先生
はじめに:
夢二の”樹根”が生み出した発想力
多くの書籍の装幀や挿絵にもなった哀愁をたたえ、「大正浪漫」を代表する絵となる「夢二式美人画」のみならず、詩や小説、随筆に歌謡、童話も創作した竹久夢二。そして図案家としての夢二の発想力は、黎明期だった「グラフィック・デザイン」の世界を独自にひらいていきました。
日本画や水墨画、木版画、油彩画、ペン画などにわたる絵画から、広告宣伝物や日用雑貨にまで広がった夢二の世界は、中央画壇からそっぽを向かれた夢二が、新しい応用美術としての「デザイン」に取り組んだ賜物でもありましたが、そうした創作の源流には、夢二の幼少期の体験や記憶、童心に描いた「絵」だけでなく、童話や短歌、小唄も幼い頃から創っていたのです。
まさに夢二の”樹根”にあったものが、「夢二式美人画」に引きずられるようにあらわれでたものだったのです。
夢二の”樹根”には何があったのか。なぜ夢二は、抒情溢れる「夢二式美人」とも呼ばれる美人画を数多く描くようになったのか、一緒にみてみましょう。
「夢二ワールド」の根源になった生まれ故郷
竹久夢二(本名:竹久茂次郎 たけひさ もじろう)は、明治17年(1884年〜1934年)9月16日、岡山県邑久(おく)郡邑久町本庄村に生まれています。現在、邑久町は、2004年に、夢二の愛した牛窓港がある牛窓(うしまど)町と、長船町と合併し、瀬戸内市となっています。
瀬戸内市はその名称のごとく、瀬戸内海に面した風光明媚な地域で、とくに島々が点在する牛窓の海岸は、「日本のエーゲ海」と称されています(実際、日本のオリーブ生産地として香川県の小豆島とともに名前が知られている)。
「日本のエーゲ海」の光輝く光景は、写真家・緑川洋一の写真集『瀬戸内海』などで、1960年代からその美しさが広く知られるようになりました。「色彩と光の魔術師」とも呼ばれた写真家・緑川洋一もまた、夢二と同じく邑久町に生まれています(緑川洋一は、植田正治、秋山庄太郎らとともに写真家集団「銀龍社」を結成)。
邑久町の中でも緑川洋一が生まれた虫明という地区は、瀬戸内の海に面していましたが、夢二が生まれた本庄は、龍王山などを越えた裏側の山麓に広がっていました。夢二の生家・竹久家からは、吉井川一帯に広がる邑久の街並と千町平野を一望でき、瀬戸内海に負けず劣らない美しい夕陽を見ることができました。
最も「日本のエーゲ海」と呼ばれる遥か以前から、牛窓港は、『牛窓の瀬戸の図』として北斎によって描かれた景勝地で、さらに古くは「牛窓の浪の潮騒島響み、寄せてし君に逢はずかもあらむ」と万葉の歌にも詠われていました。
この牛窓の港から北西部に広がる千町平野へ向う街道の途中、数キロ先に竹久家はありました(ちなみに後に夢二が日本橋に開いた趣味の店の名は「港屋」だった)。その街道は、老樹の根の如く、日本三大奇祭りの一つ「裸祭り」が催される西大寺へとまた通じ、あちこちに水郷すらも発達し、田舟で西大寺へ移動することもできたといいます。
また街道や牛窓港からは様々な流行りものや風俗が流れ込み、街道筋にある宿場は宴遊で賑わい、村芝居も盛んだったようです。『竹久夢二』(青江舜二郎著 中公文庫 昭和60年刊)によれば、竹久家は村の顔役として「地芸」と呼ばれた村芝居のパトロンになっていて、近隣の村々へ「地芸」をもってまわる勧進元であったといいます。
そのため竹久家には、村芝居のためのいろんな衣装からお面、鬘(かつら)が保管されていて、竹久家を舞台にして、芸人たちがお面を被って浄瑠璃に合わせ「面芸」を振る舞っていたといいます。
ために夢二は、浄瑠璃の文句をよく覚えていたようです(幼い頃から枕元で「阿波鳴門」を聞かされ育ったという)。「地芸」「面芸」のみならず、村芝居での越後獅子や稚児行列、西国三十三カ所巡りのお遍路さんの世界とも幼少期から接っしていました。
竹久夢二(2)へ続く:
参考書籍:『竹久夢二』(青江舜二郎著 中公文庫 昭和60年刊)/『竹久夢二正伝』岡崎まこと著 求龍堂 昭和59年刊)/『夢二郷土美術館所蔵 竹久夢二ー名品百選』(夢二郷土美術館 平成12年刊)
竹久夢ニ(2):女性と接する度合いが多かった幼少期
竹久夢ニ(1)から:
3歳の頃から馬の「絵」を描きだしていた
邑久町の旧正月は賑やかでした。とくに西大寺の観音様の会陽(えよう)「裸祭り」には、父・菊蔵も張り切って繰り出したといいます。
母と夢二たちが田舟に乗って数日後に出向けば、西大寺境内は様々な屋台が並び、太鼓や笛の音、じんたのクラリネットが奏でられ、のぞきカラクリに猿の曲芸、猛獣使い、一寸法師の綱渡りの絵看板が掲げられ、夢二を夢中にさせました。
また、大智明権現の春祭で催された競馬や吉井川の河原で見ることができた草競馬も、幼少の頃から夢二を虜にしていました。
夢二が3歳の時、初めて描いたのは「馬の絵」で、7歳の時に馬に乗っています。夢二の最初の妻となる岸たまきは、まさに馬のようにくりくりした大きな目をした面長で、目と目の間が少し離れていて、体躯は大柄ですんなりした女性だったと言われ、夢二の幼少期よりの馬好きが反映された女性だったともいわれています(『竹久夢二』青江舜二郎著)。
「夢二式美人画」の”根っ子”が、3歳の時から描きはじめた「馬の絵」と、夢二の女性好きー女性と接する度合いが多かった幼少期ーなどが絶妙に絡まったものだとなれば、「夢二ワールド」は俄然興味深くなってこざるをえません。
「夢二ワールド(式)」は、夢二が東京に出てから様々な流行や伝統を吸収しクリエイトしたのではなく、また神戸の中学で港のエキゾチズムに触れて感性が開眼したのでもなく、その原型と土壌はすでに夢二の郷土で、その身辺からたっぷりと刷り込まれ、夢二の感性と情緒を底から育んでいたのですから。
大好きだった6歳年上の姉・松香。
そして妹と、3歳年下の初恋の人
「夢二式美人画」は、郷土の文化環境や美しい自然だけでなく、竹久家の家庭の中からも紡ぎだされ染めあげられていました。
母・也須能は、子供たちに似合う柄の布を仕立て、色鮮やかな子供着や家族の仕事着をいつも縁側で手織っていたといいます。自分で繰った糸を壷に入れて様々な色に染め上げ、シマ目を数えて納屋で糸を繰り、色彩と柄を工夫してつくりだすのが母の趣味であり日々の営みの一つだったのです(母は足が少し悪かったこともあり田畑で働けなかった)。
伯父(邑久郡玉津村)が紺屋を営んでいたので、若い頃に母もそうしたノウハウと作業を覚えたようです。また、母は夢二が物ごころつくかつかぬか頃に、率先して「いろはにほへと・・・」を教え込んでいます。絵の面では、母方の年上の従兄が絵を描くのが好きで、うまく描けると夢二に絵をよく見せていたといいます。
そして6歳年上の姉・松香の存在は、夢二の感性の下地を育むに充分でした。桃割れを結い、野菊やウツボ草を髪にさしていた姉が夢二は大好きだったことはよく知られています。
一緒に家の裏手の妙見さんの丘や、道の向こう側の国司様の丘にのぼって大樫の下にゴザを敷いては、カヤツリ草で遊んだり、オオバコの芯で引っぱりあったり、アザミの花を摘んだりしていつも一緒に遊んでいました。
また6歳下の妹・栄が歩けるようになると、そこに妹もくわわるようになりました。「夢二ワールド」の根源には、姉と妹の存在があり、小学校にあがってからは、初恋の女の子、宇津木美津野(3歳年下)がそこに加わるのでした。
夢二が小学校4年の時、こうした夢二の世界に大きな亀裂が入ってしまいます。最愛の姉(17歳頃)が嫁いでしまったのです。
少年夢二は、突然、姉がいなくなってからというもの子供部屋の廊下にいつも涙をためて一人立っていたといいます。大切なものが根こそぎもぎ取られてしまったようで辛くて悲しくて仕方なかったのです。
そうなると小学校の初恋の女の子、宇津木美津野に意識がどんどん向いていきます。美津野は3歳年下の丸顔の女の子で、いつも着物の袂(たもと)に赤や紫、青の糸を沢山入れていました。
「美さんの袂は、私には容易ならぬ聖地であった」と後に夢二は語っています。絹糸でかがった手鞠、友禅の布でこさえたお手玉が飛び出てくる美津野の袂は、少年夢二にとってまさに魔法の蔵でした。
その魔法の小さな暗い蔵から出てくるのは色鮮やかなものばかりで、それもまた女性的なるものへの憧憬を強化したはずです。夢二の後に夢二は絵や詩に少女美津野を描いています。(『竹久夢二正伝』岡崎まこと著 求龍堂 昭和59年刊)
校舎を出て、対象を思いのままに描かせ、
全国の小学校の図画指導に革新をもたらした担任の先生
数え8歳の時、地元の明徳小学校に上がった夢二は、「絵」に夢中になっていきます。
この小学校時代に、夢二は自身最初で最後の絵の先生と出会っています。小学校の担任の服部先生でした。
服部先生はちょうどその時分、「1時間写生教授の実際」と銘打った研究を発表し(全国小学校教員大会にて)、初等教育での革新的な図画指導をぶちあげて注目された先生でした。つまり教室内ではなく、子供たちを校舎から外に出させて、教科書を使わず何ものにとらわれず、描く対象を決めたら自由な雰囲気で思いのままに「写生」をさせたのです(校庭に生えていた植物のソテツや宮の鳥居など、先生がまず皆で描く対象を決め、それを自由に写生させた)。
この教室外での「写生」授業を提唱したのが、夢二の担任になった服部先生だったのです。服部先生は他の授業でも、教科書抜きの型破りな授業をして学校に激震をはしらせていました。
た、絵を通じ友達になった3歳年長の正富由太郎(後に民衆詩人になる人物。父は村長も務めた)は、邑久の地方では珍しい絵本や雑誌を持っていて夢二に刺激を与えました。
2人で一緒に、今でいうグラフィティ・アーティストのように、大師堂などの神社仏閣の壁や塀に、墨や鉛筆をもちいて絵や小唄をかいて回ったのです。その落書きは友達や大人もうならせるできだったといいますが、父の知るところとなり土蔵に入れ懲らしめられたりしています。
夢二は絵の他にも、童話や短歌、小唄などをつくっていましたが、それも夢二の「マインド・ツリー(心の樹)」が、いかに広く深く、郷土の文化や芸能、村や竹久家を訪れる芸人と接していたかを物語っています。
それは夢二の才能の芽になっただけでなく、気質にもなっていきました(後年、芝居などの楽屋に気楽に立ち寄ったり、気になった芸人とすぐに打ち解けることができたという)。
母方の祖父・津田紋三郎は、とくに絵心に富んだ夢二を画家にしたいと望んでいたのですが、父は確実な仕事に就かせるため実業に向うことを望んでいたのです。
ジェームズ・ダイソン(2):「ランニング」「絵画」と「木工」が得意に
周りには「歯が立たないことにあえて挑む頑固で意地っ張りな子供」と映っていたダイソン少年は、一方でかなりの無精で(後に好奇心の塊になるダイソンであっても小さな頃はかなり無精な性格だった)、友達もうまくつくれず陰気になるばかりで、成績はずっと低空飛行でした。
そんなダイソン少年のエピソードといえば、音楽好きではなかったにもかかわらず学校の朝礼で学校のオーケストラに欠員があることを聴き、演奏の難しさも知らないまま全く知らない楽器バスーンに挑戦しようと行動したことでした(ロイヤル・フェスティバル・ホールで演奏する夢が一時ふくらむ)。
小学校時代のもう一つのエピソードは、長距離レースでのまさかの優勝でした(成長が遅かったがこの頃、体格が一気によくなった)。優勝が契機になり、ノーフォークの砂丘を走り込みはじめます(有名な陸上選手ハーブ・エリオットに関する本を数冊読み、鍛錬に最もよいのが砂丘を走ることと知ったため。なんと日々朝食前9キロ、午後は学校のラグビー、夜10時からも9キロ走っていた程。そのため授業中いつも居眠り)。
>>
「ランニングって素晴らしいものだ。互いに依存しあうチームスポーツじゃないから、自分にとって結果は一つしかない。他人より速く走るか走らないか、それだけ。勝負では、結果がすべてだ。僕はいかに何かを行ない、目に見える結果を出すかをレースから学んだ。
その意味では、後日、自分の絵が誤った主観的基準で曖昧にしか評価されない美術の世界から、良し悪しが単純に決まる技術の世界に移ったとき、とてもよく似た経験をしたと思う。…
ランニングはいろんな形で、青春時代を通じて最も重要な教訓を僕にあたえてくれた。競争力を維持する身体的、心理的な強さにはじまり、粘り強さ、不安の克服法も学んだ。いつか後ろから追いつかれるんじゃないかという不安を募らせ、先頭に立つためになおさら厳しい鍛錬に励んだ」(『逆風野郎! ダイソン成功物語』ジェイムズ・ダイソン著 日経BP社 2004年刊 p.37)
<<
また9歳の時、人生で初めての賞を「絵画」でもらいます(いつも走っていた砂丘を油絵で描いたもの)。その時の副賞がトランジスタラジオだったこともあり「成功」の旨味を初めて知ったといいます。
ところが、その成功がもたらしたものは義務感(以降4年間、学校の美術教師が率先して指導)で絵を描きくことが嫌に。この躓(つまず)きが少年時代の反抗期と重なり、それが他の面にまで影響し、再び13歳まで無精で不活発になり成績も悪いままに(議論や質問することもなく何事も興味をもてなかった)。
15歳の時、気持ちが上向きになり再度「美術」に向かいます。キャンバスに茶系の絵の具を塗りたくり引っ掻き、意識的に独自のスタイルを生みだす意欲があらわれた絵で、再び賞を獲得しはじめるのです。
この頃、後に学校で教わって唯一役に立ったことと語る「木工」に出会っています。この「木工」は、ダイソン少年の重要な”根幹”となっていきますが、古典の風土をもつダイソン家では、当時「木工」は教育のない人が粗末な小屋でするものという認識しかなく、自分もそう思い込まされていたようです(ギリシアのポリスの頃から西欧の底流を流れる意識として、自分の手でモノをつくれないことを自慢する一般的風潮があった)</span>。「木工」だけでなく自動車やテレビの「仕組み」にも興味をもってはいけない空気があったといいます。
そんな家庭環境のなか、ダイソン少年が「モノづくり」の世界の面白さを決定的に開眼させられることになったのは友達の家でした。友達の家はケント州にあり、毎年二週間ほどその友達の家に滞在していたといいます。
「友達の家」で何が行なわれていたのか。そこは印刷工房でもあったのですが、手先が器用な友達の父が自宅裏の作業場でガソリンエンジンや小型の蒸気エンジンをつくり、ボートから小型エンジン付きの飛行機、列車までもつくっていました。
その光景は後にダイソンがデュアルサイクロンを開発をした時の自宅の仕事場そのものだったようです。ダイソン少年は見よう見まねで試行錯誤して旋盤の使い方を覚えはじめ、不器用だと思っていた自分自身の新たな可能性を感じ取りだし、家で投光照明システムなどを製作。
が、ことごとく失敗に終わったといいます(自分や友達を感電させるだけだった)。結局熱意が半月続いた後、機械部品が散乱するだけでした(しかし重要な体験の積み重ねだった)。
とにかく人文系の家に生まれ落ちた少年が、世界を驚かす「エンジニア」で「発明家」になるにはさらに複合的な”根っ子”、思わぬ体験が幾つも積み重ねらなくてはなりませんでした(最も父が9歳で亡くなったため人文の引力は一気に小さくなったが、ある意味方向舵を失ったことにもなる)。
人生とはこれほどまでに迷宮であり、闇であり、「光」はあまりにも遠くにしかないことがダイソンの例からもよくわかります。そして恐らく多くの方にとってもそれは真実ではないでしょうか。ダイソン少年は”根っ子”がもがれた様に彷徨いだすのです。
<span class="deco" style="font-weight:bold;font-size:medium;">十代半ば、体力がついたダイソン少年は一時期水泳選手を夢見ますが、学校競技で大失敗。行き先を失ったエネルギーは今度は「演劇」へ。シェイクスピアやモリエール、シェリダンなどで役を演じだすのです<span class="deco" style="font-size:small;">(前述した様に父も熱心なアマチュア俳優で演劇好きだったことを思い出されたい)</span>。</span>
>>
「…いまの僕があるのは、結局は演劇があったからだ。…演劇は僕の意固地な性格にまさにぴったりだったね。…演技に決まりはない。誰かに教えを乞うこともできない。自分なりの演じ方を見つけなきゃならないんだ。
…やがて、その後のすべてにおけるように、演劇が思ったより手ごわいことに気づいた。でも、僕の創造に対する幼い衝動が最も強烈に刺激されたのは、舞台美術だった」(『逆風野郎! ダイソン成功物語』 p.44〜45)。
<<
パウル・クレー(3):母が全身不随の病、一家の風景が一変
「音楽」への愛が深まったにもかかわらず、
「不安」が生じてくる
パウル・クレー(2)から:
10歳の時、少年パウルはギムナジウム(高等中学)に入学します(入学試験は免除されている)。学校では当初、とりわけ生物学や数学、古典語と、パウルは熱心に勉強し、成績も上々でした。博識な父からたくさんの刺激を受けたことも勉強へのヤル気につながっていたようです。
この年、パウルはオペラを初めて観劇しています(おそらく両親に伴って)。演目は『吟遊詩人』でした。パウルは大興奮します。これ以降、パウルのオペラ観劇はずっと継続されます(バレエは一度だけだった。演劇・歌劇には俳優が別人格にまるっきり変身することの魔術性と舞台風景にパウルは惹かれつづけた。芝居を”本”で読むことも異常に好んだ)。
クレー一家は定期演奏会通いもかかさなかったので、パウルの「音楽」への愛も深まっていきます。イタリア古典歌曲(ランディ)にはとくに深い感動に浸されています。バッハのソロ・ソナタを弾いていると、スイスで高い人気を誇っていた画家ベックリンの作品がとるに足らないもののようにみえてくるのです。
ところが、少年パウルの内で次第に獏(ばく)とした「不安」がつのってくるのでした。四行詩を幾つも書きだしたのもこの頃です。そしてスケッチブックを手にし何やらものを描いている時にだけ、どこからか「希望」ともいるような清々(すがすが)しい感覚を覚えるのでした。
窓ガラスに映る<自分の姿>を「観察」すると、いつもとは異なる感覚で満たされたといいます。以前にも何度も自らに問いかけ、<自分自身>のことを掴みとろうと”研究”してみたといいます。が、結局いつもはうまく探れなかったのに、今回はパチッと何かが弾け、「理解」できたというのです(10歳を少し過ぎた時のこと)。
一家の風景が一変、母が全身不随の病に。「文学」に熱中
その翌年、11歳の時、得意だった数学の授業で、これまでにはなかったことが起こります。質問にまったく答えることができず、先生から「もっと勉強しなさい! もう座ってよろしい」と告げられたのです。
少年パウルは、「眠っている力をそっと隠すのだ」とこの頃、思っていたようです(見えない存在になろうとしたカフカの様に)。
そして「外側では微笑み、内側でもっと自由に笑い、魂には歌、唇には小鳥の囀(さえず)るような口笛を吹いて」「どこへ行ってもいい。私には確信がある。私は自然を愛している、自然は私を慰め、約束をしてくれる。私は<不死身>だ」と。
5年続けてきたヴァイオリンの調弦が上手くできなくなったり、絵も描けず、詩も書けない心理状況が繰り返し巡ってきたようです。
ヴァイオリニストになろうと思ったことはない、と日記に書いています(11歳の時)。
自分には華やかさが欠けているんだと。パウルの意識は内側に向かい、叙情的な詩の詩集をつくる計画をしたかとおもえば、エロティックな詩を書いたり、自主的に参加していた読書会で(おそらく父とともに)ソフォクレスの『アンティゴネ』を読んでいます。短篇小説を幾つか書いたのもこの頃でした(この年に全部処分)。
次々に代わるオペラのソプラノ歌手への憧れ。一夫多妻の考えすら浮かんだという行くあてのない衝動ばかり。途中、ギムナジウムを辞めたいと両親に告げていますが、反対されています。以降、受難の日々がつづきます。
パウル14歳の頃から、クレー家の風景は一変します。パウル自身もひどい盲腸炎に罹っただけでなく、母が全身不随となり、以降20年以上にもわって病床に臥さざるをえなくなったのです(室内中に呼び鈴がとりつけられた)。重い病を患っても母は気丈に振る舞いつづけたといいます(クレー42歳の時に母、逝去)。
パウルの心の内では、「文学」への関心が膨らむばかりでした。シェークスピアにセルバンテス、オビディウス、モリエール、イプセン、ヘーベル、オスカー・ワイルド、ゾラ、トルストイ、チェーホフ、ゴーリキィ、ショーらの作品を手当たり次第に読みまくります(ギリシア語への強い関心。ギムナジウムの卒業時には文学士の資格を得ている)。
パウルが「日記」を書きはじめたのは、ギムナジウム卒業真近かからでした。「日記」はその日の体験や考えに加え、読んだ本のタイトルにそのコメントも付けられ、本に関する事柄で溢れていました。少年パウルは、汲めども尽きない疲れ知らずの「読書家」になっていたのです。
父の反対を押しのけ、母はパウルをミュンヘンの画塾に送り出した
好奇心に溢れた「読書家」パウルでしたが、学校の成績はさらに落ち、お仕置きに両親はパウルを修学旅行に行かせなかったようです。ギムナジウムの卒業試験は落第点より4点上でぎりぎり試験に通り、修学旅行の代わりに一人で遠出し、スケッチブックと色鉛筆を持ってビール湖にある島に初めての写生旅行に出掛けます。その時、パウルは自分は「風景画家」だと深く感じたといいます。その思いは強くなり、ミュンヘンに絵を習いに出たい衝動を押さえることはできなくなります。
ところがその思いは、「音楽家」としての将来を見込んでいた父とついに衝突することになります。クレー家のなかで、パウルの多彩な才能を感じ取っていたのは母でした。祖母や親類縁者との付き合いから、どれほどパウルが絵を学びとってきたことか。またその絵と絵に熱中するパウルの姿には、ヴァイオリンの演奏会の様には人々を魅了することはできていないにもかかわらず、特別な何か(才能)が不思議な息子パウルに潜んでいることを感受していたようです。音楽の道を歩んできた母イーダは、ひろい芸術的感性をもっていた女性だったのです。
母は父の意向をつっぱね、息子パウルの気持ちを汲み絵描きへの道を選ばせ、絵画熱が沸騰していたミュンヘンへと送り出します(母は親類縁者をたぐりミュンヘンの知人の住所をパウルに持たせ送り出した)。気負ったパウルは狙っていたミュンヘン美術専門学校(アカデミー)に自分の作品を持ち込んだのですが、画塾で予備教育を受けるように諭されます。大都会の空気に触れたパウルは、ミュンヘンには3000人以上もの若き絵描きがいて、自身もその内のひとりに過ぎないことをひしひしと感じざるをえませんでした。
一方、パウルはまだ気侭なもので、ハインリッヒ・クニールの画塾で知り合った仲間たちとリヒャルト・シュトラウスやヴァインガルトナーといった当時の名指揮者がタクトをふるう演奏会やオペラ観賞に夜ごと繰り出すのです。
ただこの画塾で、年配の退役大尉から手探りするように描く方法を教えられ(裸体デッサン中心)、パウルはあっという間に頭角をあらわし画塾の期待の星となったのです。期待の星として次年度の入学を目指したパウルでしたが、実際には入学に2年かかっています。パウルはこの頃、ミュンヘン美術専門学校を出ておくのは、将来の生存競争を生き抜くためにも必要なプロセスであり、後に大学に通って文学と哲学、美術史を勉強する考えがあることを母に手紙で書き送っています。
ミュンヘン修業時代に、3歳年上のピアニストの女性と出会う
このミュンヘン修業時代は、パウルにとって必要不可欠の待機時間であっただけでなく、決定的な出会いをもたらしています。人生は面白いもので、その人にとって生涯無二の存在(たとえば生涯の伴侶)は、人生の目標が到達された後にあらわれるというよりも、暗中模索しながら前進している時にこそあらわれることがえてして多いということです(無論様々なケースがあるものの、今日とちがって結婚年齢が格段に早かった時代は往々にそうしたケースが多かった)。
そうした時期に出会った人は、立場がつくりだすイメージや人間関係、環境ではなく、その人の内面から沸き上がる人間性そのものの魅力に感じ深い付き合いがもたらされます(ために、破局も頻繁ではあるが)。パウルが出会った女性、リリー・シュトゥンプフともまたそうした女性でした。リリーは3歳年上で、母イーダと同じくピアノストでした<(つまりリリーは、母イーダと同様、音楽をよくしながらも、やわらかい芸術的感性をもち、パウルにとっては遠く離れて暮らす母親的役割を担ったでろう)。
出会いは、画塾ではなく、母の友人を通じてとりおこなわれることになったバッコーフェン夫人宅での家庭演奏会での事でした(20歳の時。ミュンヘンに来てから1年以上たっていた)。そこにピアニストとして招かれていたリリーに、パウルは一目惚れしたのでした。バッコーフェン夫人宅や母の友人宅で繰り返し催された家庭演奏会で、2人は頻繁に共演を重ねます。パウルは感情の嵐となって接近するが、リリーはキスをしてもそれは友情としてのものだと割り切り、好きな男性がいることを打ち明けます。
パウルは愛を勝ち得るために、リリーを魂を鷲掴みにするような求愛をし、それが叶うのです。穏やかでピースフルなパウル・クレーの作品ばかりを見ていると勘違いされる人もいるかもしれませんが、パウルは性格・気質的にはまったく”草食系”ではありません。愛を込めて情熱的に行動することは、自分の”天分”だとも言っているくらいです。それは若い頃のパウルの顔つき、目力をみれば一目瞭然明らかなことです。
さて、リリーの父は衛生参事(高級官僚の医師)で、妻を失ったのち娘リリーより僅かに年上の若い女性と再婚、娘の結婚相手も口をさしはさみました。父にとって相手はあまりにも想定外(規格外)の、定職のない、将来が何も約束されない芸術家志望の若者では、結婚を了承することなどもっての他でした。父は娘の結婚相手は医者か将校であるべきだと考えていたのです。しかもパウルはせっかく入学したミュンヘン美術専門学校(アカデミー)を、学ぶべき方向性を見出せなかったとして僅か半年で辞めてしまっています(実家の学資援助が底をついたといわれています。パウルはこの時いったんベルンに戻っている)。
2人は出会った1年半後に婚約の約束をかわしますが、それを知ったリリーの父は娘と縁切り(廃嫡)<します。最も2人がすぐに結婚しなかったのは、リリーからパウルに対しある提案がなされたからでした。それは結婚はパウルが仕事でも人間的にも成長できてからのこととし、その期間を8年としたのです(自身もその間にピアニストとして成長したいと伝えた)。
父への反抗心から安定の保証もない美術家志望のパウルと一緒になったリリーでしたが、立派な職の身分(医師か将校)の男性に好意を寄せていた時期がありました。しかしリリーは、パウルから流れ出てくる「異常な力」を逞(たくま)しく思い、信じていたので、パウルとの婚約は堅持されたのです。
そしてこの「異常な力」は、母イーダも同じ様に感じ取っていたからこそ、父の反対を押してパウルを信じて絵の道に向わせたとおもわれます。さらにいえばその「異常な力」は、母方の家系に伏流していたものなのかもしれません。それが祖母から「絵」を媒体にして伝わった。左利きだったパウルを直そうとした時、祖母は感情のおもむくまま使いやすい手で描いた方がいいとして、つっぱねています。
21歳の時、半年に渡るイタリア「遍歴時代」
入学した美術学校で割り当てられたのは、2年前にミュンヘンで分離派運動を興した美術学校に着任したばかりのフランツ・フォン・シュトゥックのクラスでした。神秘的で象徴派画家のシュトゥックは、ルネッサンスの芸術家たちのように多様な側面をもち、版画家であり彫刻家であり建築家でもありました。
講義には美術史や解剖学もありました。同じクラスで学んでいた生徒のなかに、ロシア出身のワッシリー・カンディンスキーがいて、後に強い関係で結ばれるようになります。シュトックはパウルにリュマン教授のもとで彫刻家としての修業をはじめてはどうかとか(実現されなかった)、別の教授のもとで版画の技法を学ぶようにと薦めています(イタリア遍歴旅行から帰り、成功した最初の作品の一つは、エッチングでなされた「樹のなかの処女」だった)。
21歳の年(1901年)、パウルは学生仲間で彫刻家のヘルマン・ヘラーと連れ立って、ゲーテやデューラーのようにイタリア旅行に出掛けています。パウルの「遍歴時代」でした。ミラノからジェノバ(ここでパウルは生まれて初めて海を見る体験をしている)、リボルノ、ピサ、ローマ、ナポリ、フィレンツェへと巡ります(半年に及ぶ)。
ナポリでは初めて水族館を訪れ海の生物の奇怪な姿形に、またナポリの海岸にすっかり魅了されています。そしてボッティチェリにラファエロ、ダ・ヴィンチの聖ヒエロニムスにシスティナ礼拝堂のミケランジェロ、ペルジーノ、ヴァティカン美術館の彫刻群、初期キリスト教美術、ポンペイの絵画、各地のルネッサンス建築とゴシック建築(バロック建築には感性が合わなかった)の謙虚な弟子と化し、またドニゼッティやプッチーニ、マスカーニ、ワーグナーのオペラ公演、さらにはイタリア式の話し方や振る舞いを観察しています。
「多くの事柄が私の内部の奥深くで変わっていく」とパウルが語るように、成長しつづけていたパウルの「心の樹」が、様々な刺激と感応、影響を受けて、一挙に激しくふるえ、”流動”し変容し、伸長しはじめたのです。
・参照書籍:『パウル・クレー』フェリックス・クレー著 矢内原伊作・土肥美夫訳 みすず書房 1978刊/『新版・クレーの日記』W.ケルステン編 みすず書房 2009年刊/『クレーの食卓』林綾野、信藤信、編・著 日本パウル・クレー協会 講談社/『パウル・クレー』エンリック・ジャルディ著 美術出版社 1992年刊/『パウル・クレー:絵画のたくらみ』前田富士男、宮下誠ほか 新潮社 2007年刊
パウル・クレー(2): パウルから流れ出てくる「異常な力」
音楽への深まる愛と不安。母が全身不随の病に。疲れ知らずの「読書家」。父の反対を押しのけ、母はパウルをミュンヘンの画塾に送り出した。パウルから流れ出てくる「異常な力」とは
物事に没頭しだすと異常なほどに熱心に
3歳頃までの幼い頃、パウルは姉と同じようにスカートを履いていて、それがとてもお気に入りだったのに、ある時、自分が女の子ではなく、可愛らしい衣装を身につけることができないことを知って悲しんだといいます。パウルはかなり早いうちから美しい小さな少女たちの印象が強烈で、同じようにフリルのついた可愛らしい衣装を着れなくなっても、5歳までは女の子のように人形と遊ぶのが大好きでした。
3歳から5歳まで、パウルは女の子でないこの頃の記憶としては、自分が女の子ではないので、スカートの下に素敵な白いレースのついたズボンを履けないのを悲しみます。そのためなのか、大好きだった人形や物を窓から外に投げだすのが癖になってしまいます。
絵や人形遊びだけでなく、空想の羽根をのばしながらあれこれ「演技」するのも大好きだったのですが、演技中に時々、「ぷぅー!」という嘲笑するような声が聞こえてきて心をかき乱され我慢できなかったといいます。その声の主は父でした。
幼い頃からずっと、父を絶対的な存在で、「パパは何でもできるんだぞ」という父の言葉はそのまま真実として受け入れていたので、その思い込みは少しゆらいだりしたようです。
こうした繊細にして抵抗力のある気質は、父ではなく母から受け継いだもののようです。またこの年頃から物事に没頭しだすとその熱心さはふつうでなく、几帳面な程にずっと取り組んでいたといいます。たとえば部屋の隅にあったカルタ遊び用の小さな机に向って絵を描きだと、うずくまるようにしてずっと描いているように。母はパウルを少しでも庭に出して外気を吸うようにと考えよく部屋から追い立てたりしたといいます。
「童話」がよく読まれたクレー家。
叔父さんの所でユーモア雑誌をよく見る
クレー家では音楽だけでなく、「童話」もよく読まれたようです。パウルはそうした物語を暗記していて成長してからも物語ることができました。小学校にあがる前から、パウルは人形芝居が好きになっていて、とりわけ道化役がお気に入りでした。これもどうやら母方の人物からの影響だったようです。
母方の叔父エルンスト・フリック(フリック叔父さん。レストランを経営していて。パウルはスイスで一番のデブだと日記に記している)がパウルのためにと新聞のなかから劇場のチラシを切り取ってくれていて、パウルはそのチラシを集めていたという記述があるからです(『パウル・クレー』フェリックス・クレー著 みすず書房)。
人形芝居の観客は、姉とクレー家の女中と近所の子供たちでした。パウルはこのフリック叔父さんのレストランによく連れていかれたようで、そこで絵を描いたり、絵入りの週間ユーモア雑誌(ミュンヘンで発行されていたもの)をよくみていました。
また食卓のテーブルが「化石」の断面でできていて、そのグロテスクな迷宮のようなかたちを鉛筆でなぞっては紙に書きとっていました。それがパウル・クレーの「奇怪なもの好き」のきっかけで、9歳の時のことだったといいます。
フリック叔父さんは動物の鳴き真似が得意で小さな子供を騙したりしていますが、後にパウルも7歳の時、2、3歳年下の男の子たちに、お前たちは罪深い人生を送っていると責めて泣かせ、泣き出すと手の平を返して嘘だからといって慰めたといいます。
少年パウルは決して心穏やかで優しいばかりの少年ではありませんでした(『クレーの日記』は、後に他人に読まれることを意識し改竄されている部分があるという。
この日記は19歳の時から約20年間つけられ、40歳過ぎてから清書された時に「子供時代の思い出」という一文が添えられた)。9歳の時には初恋の美少女(クレーはとにかく美少女好きだった)に機会を狙いすまして強引にキスしようとしますが、激しく抵抗され失敗に終わっています。
父の繊細な職人気質。
夏には一家で森の中へ
母はことあるごとにパウルを連れ祖母の家を訪れていたようです(祖母や親類は、バーゼルからベルン市内や近郊に引っ越して来ていて、お互いに盛んな行き来があった)。そして自分の生家の人からの影響をパウルが自然に受け入れるままにしていたにちがいありません。
ピアノと声楽に優れ母イーダもまた、そうした環境に育ったからで、しかしまさか息子パウルが後に画家の道を選択することになるとは想像もつかなかったにちがいありません。
母方の人々からの影響に比べ、父ハンス・クレーの郷里はドイツのテューリンゲンだったこともあり、父方の人たちからの影響はかなり少なく、根本的な内面的接触はほとんどなかったといわれています。
最も父は、地理的にドイツ中部のやや右に位置し「緑の心臓」とも呼称されるテューリンゲン出身らしく(多くのドイツ人は森の中に入るのが好きだといわれるが)、夏には家族で森へ入っていったといいます。そして冬によくパウルを連れて行ったのは、美術館でした。
また父ハンスは、教会の日曜礼拝にオルガン奏者として手を貸していただけでなく、片手間に煙草パイプや釣針、弓矢などを自らつくるなど、その繊細な職人気質的な部分は、音楽以外にも多分にパウルにも受け継がれていったようです。
7歳の時から「ヴァイオリン」を習いはじめる。
美術を愛するヴァイオリン教師と巡り会う
クレー家やパウル・クレーの音楽的才能について知悉している人にとっては、クレーの絵画に「音楽的感覚」が色彩としてあらわされている作品が数多くあることはあらかた知ってられることとおもいます。
さらにはクレーが10歳にしてベルン音楽協会(管弦楽団)の非常勤団員になり、それ以降も持ち歩いていたスケッチブックやノート、教科書に風刺的デッサンや風景画を描いていたことも。
「音楽」も「絵画」(今日なら「イラスト」や「映像」や「写真」だろうか)もともに上手い少年少女は周りには時折りいたりするので、パウル・クレーの場合もたまたま2つのこと(実際には、これに「文学」も加わる)を”器用にこなす才能”があるとおもってしまいがちですが、クレーの「マインド・ツリー」をよくよく辿ってみれば、やはりそれぞれにしっかりした”根っ子”があることがみてとれます。
「音楽」も「絵画」は、クレーの「心の樹」のなかで、祖母がよくした「刺繍」の様に織り上げられ、重なりあい、融合していったにちがいありません。
パウルは小学校にあがった7歳の時から、ヴァイオリニストだった父ハンスと同じくヴァイオリンを習いはじめています。家では無論のこと、「音楽」で満ち溢れていたはずなので、急速に上達していったようです。
ヴァイオリンを素直に習いはじめた一つの背景には、5歳の時に大好きだった祖母が亡くなったことも幾らか関係しているようで、「絵かきとして”孤児”になってしまった。そのかわりにしばらくして、ぼくの音楽教育が始められた」とあります(パウル・クレーの日記覚え書より『パウル・クレー』;フェリックス・クレー著)。
しかしフリック叔父さんのレストランで化石の断面のかたちを映しとったり、ノートや教科書の余白に、風刺的デッサンや風景画を描いていたのは、祖母という絵の<臍の緒>と切れてしまった後のことで、すでにかなりの養分が”樹液”の様にパウルの感性に取り込まれていたためだったとおもわれます。
少年パウルは2、3年もするとヴァイオリンの腕前はかなり上がり、モーツァルトやバッハの作品も弾けるようになります(10歳の時に、ベルン管弦楽団の非常勤団員として定期演奏会に参加)。
そしてある優れたヴァイオリン教師に巡り会っています。そのヴァイオリン教師は、「音楽」以外でも少年パウルに影響を与えることになります。
またヴァイオリン教師は、スイスのバーゼル大学の教授で美術史家、文化史家として知られるヤーコプ・ブルクハルトを尊敬し、彼の著述を手引きに、美術を深く愛するひとだったのです(ブルクハルトは、当時バーゼル大学で古典文献学を担当していたニーチェの”注意”を<世界史>へうながした人物)。
バーゼルと言えば、母の出身地でもあり、大好きだった祖母もかつて暮らしていた土地でした。パウルの裡で再び留まっていた「美術」への意識と感性が蠢きはじめます。パウルは教師の書棚に揃っていた美術書に耽溺するのに時間はかからなかったようです(21歳の時に、友人と半年のイタリア旅行に出掛けた時に持参していったのが、ブルクハルトの『チチェローネ イタリア美術的観賞の手引き』だった。現地ではその書籍からのクレーの感化は限定されたものだった)。
パウルの心のなかで、絵画がまるで色彩鮮やかな「楽譜」の如く、連なりはじめたのでした。
パウル・クレー(3)に続く:

![JACK KEROUAC:KING OF THE BEATS ジャックケルアックキングオブザビート ジャック・ケルアック/キング・オブ・ザ・ビート [DVD] JACK KEROUAC:KING OF THE BEATS ジャックケルアックキングオブザビート ジャック・ケルアック/キング・オブ・ザ・ビート [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51s7EpWfMwL._SL500_.jpg)
















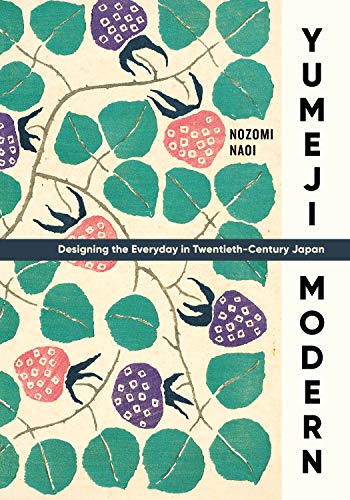





















![Pen (ペン) ぬくもりの文房具/パウル・クレーをめぐる旅へ。 2009年 2/1号 [雑誌] Pen (ペン) ぬくもりの文房具/パウル・クレーをめぐる旅へ。 2009年 2/1号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W03-FW5-L._SL500_.jpg)




